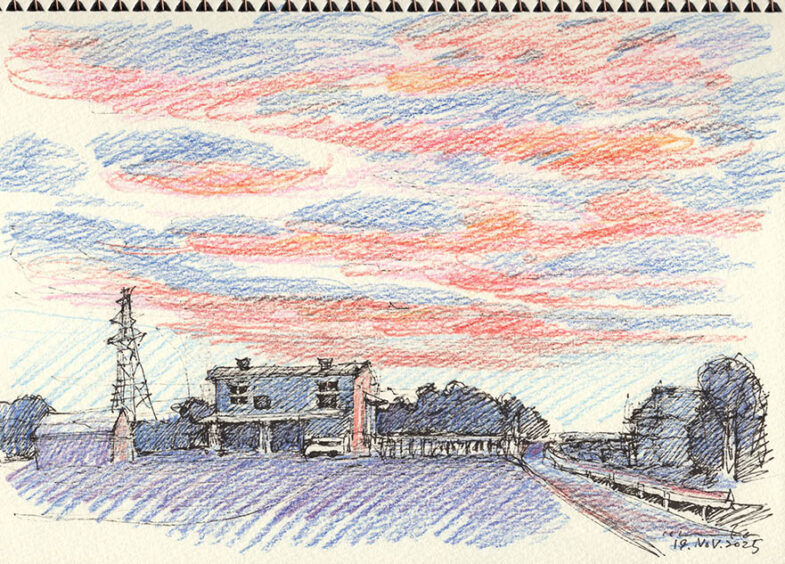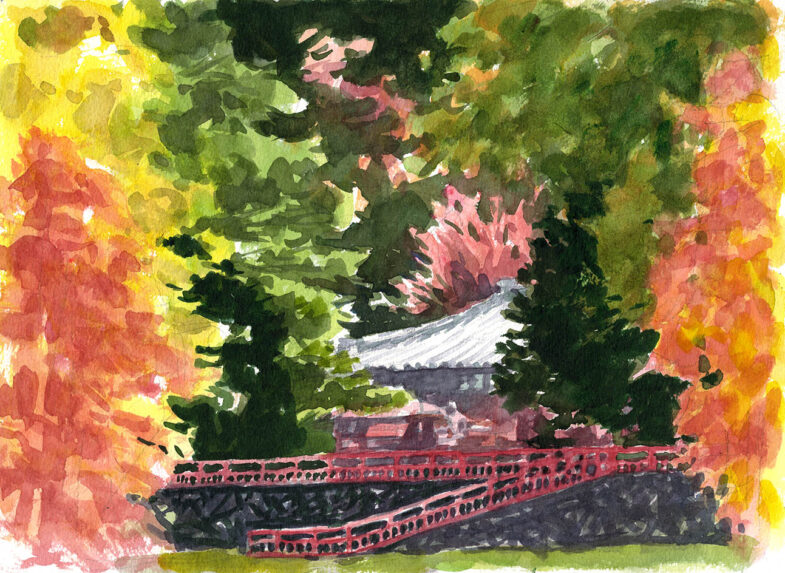
大相撲九州場所で、ウクライナ出身の関脇安青錦が、12勝3敗の相星で並んだ横綱豊昇龍との優勝決定戦で勝利。初優勝と大関昇進の2つを同時に手にした。
わたしは子どもの頃から相撲が大好きで、場所中はラジオで実況放送を聴きながらウォーキングすることが多い(テレビは見る時間がない)。安青錦は、しばらく前から相撲解説者の舞の海さんの一押しの力士らしく、ラジオで聴く限りでは、相撲の本道である「低く、鋭い立ち合い、頭を上げない」を徹底している力士なのだな、という認識があった。たとえ地味でも、そういう力士(他には若隆景など)がわたしは好きなのである。
安青錦は安治川部屋に所属している。安治川親方は技能相撲で有名だった元「安美錦」。その師匠である、元横綱「旭富士」(伊勢ヶ浜→現宮城野親方)も、この「低く、鋭い立ち合い」を徹底していた。それが横綱、照ノ富士を作り上げた(照ノ富士は引退し、伊勢ヶ浜部屋を継いでいる)、と思う。
旭富士が活躍しはじめた時期、わたしは性格的には、同年代ということもあってか横綱「隆の里」が好きだったが、いわゆる「腰高」の相撲で、短命の横綱になってしまった。弟子である「稀勢の里(現二所ノ関親方)」もその影響を受けたせいか、相撲が全体として腰高で、(他の事情もあるが)横綱としては活躍できないまま終わってしまった。低く鋭い立ち合いができていたら、もっともっと活躍できたろう、という残念感が今もある。
安青錦の相撲は、相撲の動作の基本を徹底している。それが(彼が外国人であろうとなかろうと)純粋に相撲好きなファンの心に届く。安治川親方の指導の賜(たまもの)でもあるが、それが可能になる安青錦の素質(心理面も含め)が素晴らしいのだろう。大関になっても、今の相撲を忘れさえしなければ横綱になる日は近い。