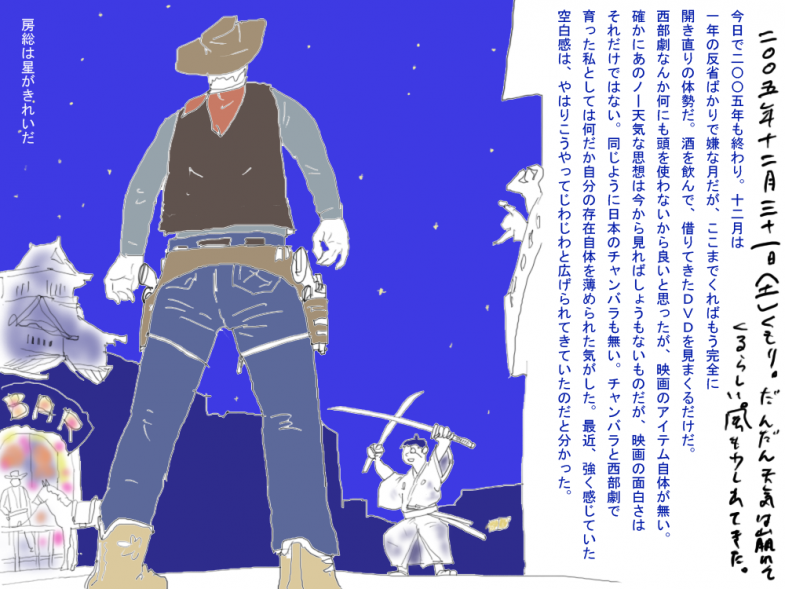ここ1,2ヶ月の間に、「瘦せましたか?」「何かあったんですか?」と何度か聞かれた。ダイエットの効果が見た目にも表れてきたということだろう。昨年10月末からのダイエット、今も継続中―現在62.5~63.5kg を行ったり来たり。体調すこぶる軽快である。ご安心ください。メタボ検診で引っかかった時が身長169㎝、74kg (コロナ前は69kg )だから、コロナ前と比べても6kg 前後減り、久しぶりに高校生の頃の体重に戻ったことになる。体重の減少は目に見えないが、腹囲が減少し始めたので、その変化が周囲にも見えてきたということだろう。
体重が 1kg 減ると腹囲はだいたい1cm 縮むという。ホンマかいなと思っていたが、本当に10cm 近く腹囲が縮まった。以前のズボンはどれもダボダボ。すべてのベルトは10 cm カットしないと使えなくなった。へそ回りの皮下脂肪の厚みはあまり変わらないが、その下の、時には前かがみが苦しいこともあったほどの脂肪はスッキリ消えた。メタボ検診で引っかかっても、本当はあまり肥満を感じていなかったが、ダボダボのズボンを穿くと、逆に検診前の体が目に見えてくるような気がする。
予想もしていなかった一番の嬉しい変化は、「睡眠薬」が不要になったことである。「頭内爆発音症候群」というのを前に書いたことがあるが、要するに頑固で意地悪な睡眠障害が長い間本当にわたしを苦しめていた。それが、やっとここ1ヶ月、服用無しで眠れるようになってきた(まだ1ヶ月だけだが)。これはウォーキングの効果だろう。
もともとわたしのダイエットの(2番目の)目的は、肥満気味の息子のためでもあった。子どもは誰でも、○○禁止とか、○○した方がいいよ、という命令的な言い方や誘導には敏感に抵抗するものだ(わたし自身がそう)。ましてや自分がメタボのくせに、ああしろだの、こうした方が、なんて言っても聞く耳など持たせられるはずがない。それで、(もちろん自分の健康が第一だが)ダイエットの効果をわたし自身が実感・実証して、彼の眼に見える資料、一種のモルモットになろうとしたのでもあった。
メタボ検診の会場には、これ見よがしに「1㎏」「3kg」と標された「脂肪の塊」の模造品が置いてある。わたしは「3kg」をこっそり手にもって、自分のお腹に当ててみた。そのずっしりした「嫌な重さ(これが金とかプラチナだったら!立ち上がれないほどあってもいいが)」。それが2、3個も自分の身体から消えた―その心地よさは、頂上に立ったときの登山の喜びがずっと続いているような―感じ。
もう二度とアレを2個も身体につけたくない。それが今の心境。