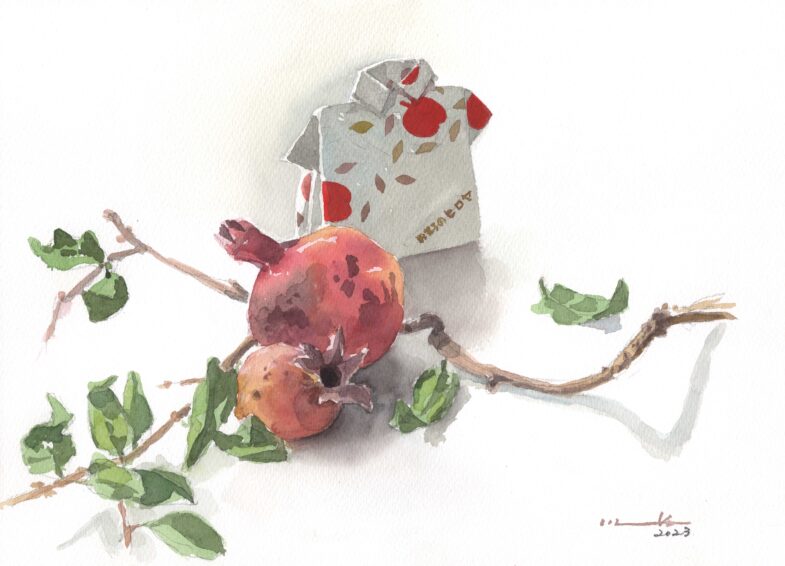青いカモメ絵画教室のスケッチ会がありました。場所は埼玉県宮代町にある、日本工業大学構内。実行委員長が入構許可をもらってくださって実現しました。天気も良く、風もそよ風で、まずは絶好のスケッチ日和(日なたはちょっと暑かったかな)でした。
スケッチブックのサイズもそれぞれ様々。かつての仲間を呼んで、おしゃべりの方が熱心な人もいたり、まあまあ楽しく過ごせたようで、それが一番良かった。わたしもお会いできました。成果は?皆さん、最低でも義理で一枚は描きました(笑)。
この絵画教室も、もとをただせばこの大学の、近隣住民に開放されたオープンキャンパス、「公開講座」にルーツを持っています。講座終了から10年近く経ち、皆さん(不思議なほど)懐かしがって、今回の企画になりました。それぞれの人にとって、友人ができる、同じ趣味の友人の輪が広がった「聖地」なのかも知れません。そういう共通の場所があることは有難いことだと、つくづく思います。
当時はずいぶんこの構内を題材にスケッチしたものでしたが、構内の様子もだいぶ変わりました。図書館や学生食堂が別の場所に新しくなり、真ん中に大きな広場ができるなど、全体的に明るく、開放的になっています。木がまだ少なめですが、成長したらちょっとした公園気分です。そこをたくさんの学生たちが、講義のある教室へ移動するためにぞろぞろと歩いていきます。
のびのび、リラックスしていて、彼らのこの貴重な時間を大切に過ごして欲しいものだと思いました。わたしたち「老人クラブ」も少し、シワがのびたように思います。この瞬間にも、 “歩行困難な老人でさえ” 容赦ない砲弾、爆撃の下を避難しなければならない世界があることを、わたしたちは知っています。スケッチなどに過ごせる、平和で楽しい時間を若い人たちにも遺していきたいものですね。