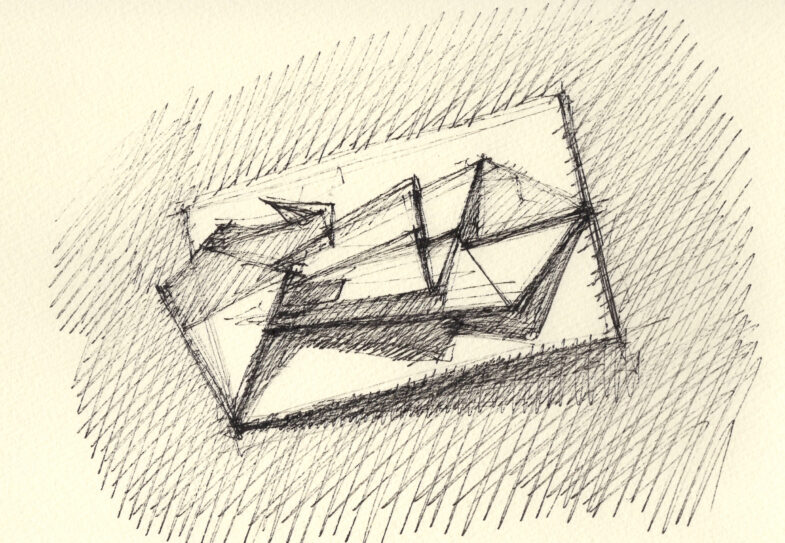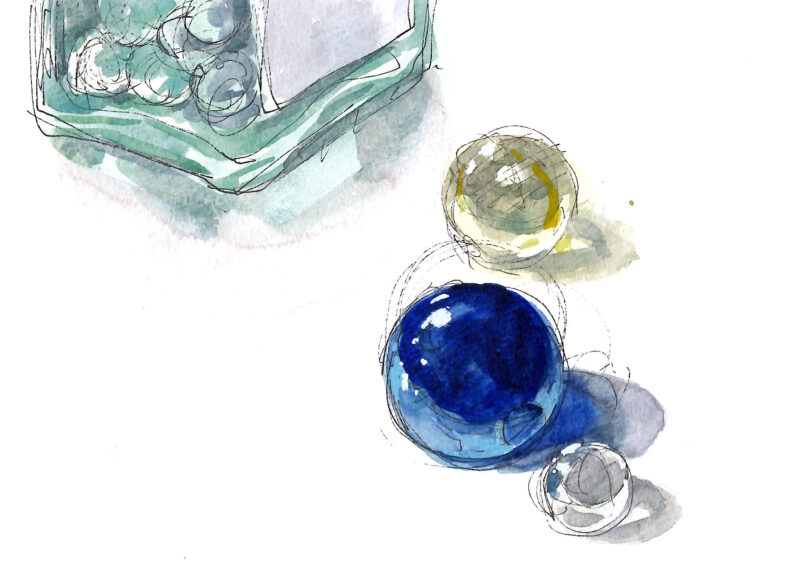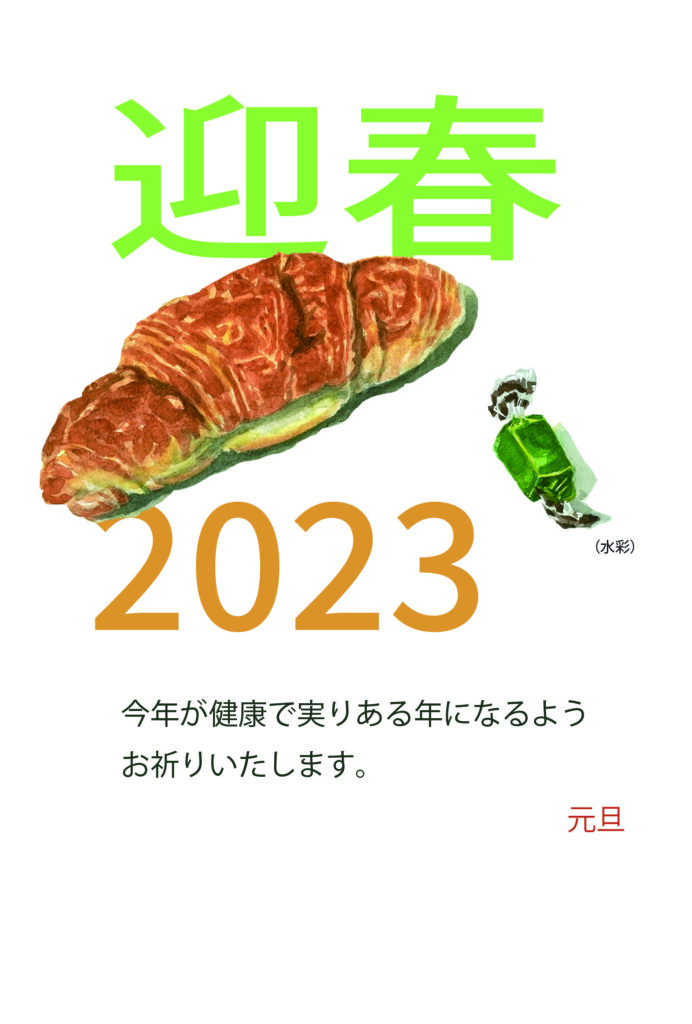
step by step (一歩ずつ)という慣用句を自分の感覚に合わせて作りなおしてみた。「一歩」というのは(わたしにとって)意外に大きく、半足(足裏の長さの半分)ずつ、見た目で言えば“すり足”のように進むことさえかなわないことがある、という意味を込めたつもり。(ちなみに、英文的には不適切な句だと思う)
毎回動画の話で恐縮だが、あるYouTuber が言うには「YouTubeを始める人のほとんどは挫折する。」最初の数カ月は一歩も進まないからだという。頑張って動画を作っても、反応がゼロかそれに近い日が続き、少し視聴数が増えても、嫌なコメントが来たりすると落ち込んで熱意を失う、のだそうだ。
幸い?わたしの場合、わりと最近まで視聴数とか全然気にしていなかった(そんな余裕もなかった)。とりあえず作る練習。作ったものをアップする。この二つを繋ぐことができるだけで100% 満足できた。そんなごく小さな技術的なことを一つ覚えるたびに、小さな喜びを得た。小さな成功体験の積み重ねというやつ?
「ほとんどの人は視聴数〇万回とか、チャンネル登録者△万人というところだけ見て、自分にも簡単にできそうだと思う」とも言っていたが、「そんなの無理」と真面目にとらえなかったのも、まだ続けられている理由の一つかもしれない。いろいろ数値や例を挙げて説明していたが、一言で言えば、結果を早く得ようとし過ぎるからということのようだった。
動画であれ、なんであれ、最初は(対外的な)結果など望めないのが普通。けれど、(自分の中では)難しかったところがなんとなくできるようになった、それらしいかたちをとれる、とるのが苦にならなくなってきた、など小さなステップアップは手応えとして誰にでもあるものだ。その小さな short step の積み重ねが step を作る。実際、皆そうやってきた。
苦しいのは、それがどれだけあれば 「一歩」になるのか、それにどれだけの時間がかかるのかが分らないということではないだろうか。今のアメリカ流の教育法の一つは 、step をできるだけ小さく区切って、具体的な目標を明示することなのだそうだ。そしてこの教育法が多くのノーベル賞受賞者を生んできた、と何かで読んだ。
これが出来ればグッジョブ、それもできればコングラチュレーション(おめでとう)、グレート!(すごい!)。(日本流に)遠いゴールだけを見て、「これくらいじゃまだまだ」と思うから苦しい、のかもしれない。自分で自分を教育しよう。人が褒めてくれなくたって自分で勝手に褒めよう。ご褒美も用意しよう。Step を さらに小さく区切って、まずは自己満足から Start from a step.