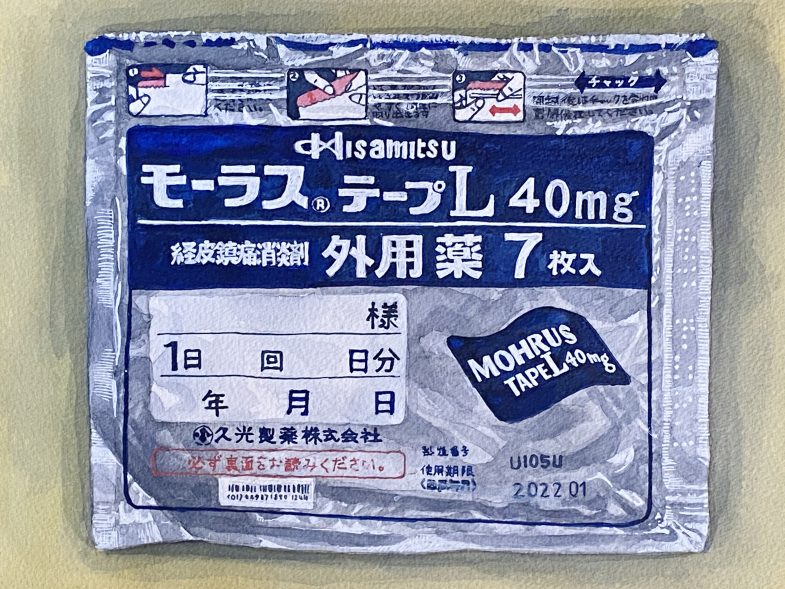目覚め前、ココシュカのポスターの夢を見た。2019年5月の「ウィーン・モダニズム」展を、大阪の植松君と一緒に見たときの絵の夢だ。もうすっかり忘れていたのに、何の前触れもなく、すっと夢の中に現れた。記憶が薄れないうちにと、とりあえず描きかけの100号のキャンバスに「バーチャル加筆」してみた(もちろんココシュカのポスターの格調はずっと高い)。
ここ1週間ほど、制作にあたって足踏み状態だった・・・方向は決まっている―描き方もほぼ決まっている―「でも具体的なイメージが湧いてこない」―イライラしながら、別の小さな絵を描いたり、アトリエの細々した片付けや作業をしながらずっと考え続けていた。が・・・何も湧いてこず、少し焦り始めていた。
オスカー・ココシュカは20世紀、たぶん「表現主義の画家」とされているだろう。オーストリアに生まれ(最終の国籍は英国。スイスにて没。クリムトやシーレなどとともに「ウィーン分離派」の運動にも参加し、目覚ましい発表をしている(年譜から初めて知ったが、バウハウスでも教鞭を取ったことがあるらしい)。けれど結局はグループに与せず、自分ひとりの世界を歩んだ人である。
正直に言うと、彼の絵は今もわたしにはよく解らず、決して好きなわけでもない。それでもなぜか作品の「重さ」のようなものが、ずっとわたしを離さなかった。―それから3年経った今朝になって忽然とそれが夢枕に立ち上がるなんて。―夢の啓示を忘れないよう、すぐ二階に跳び上がって展覧会の図録を捜索した。
夢の中で、「これだよ!」と叫んだような気がする。時計を見ると6時前。寝たのは1時半頃だから、睡眠学的にはある種の「神がかりの時間帯」らしい。「神(がいるならば)がアイデアをプレゼンしてくれた。これを活かさなければ、文字通り罰が当たる」と思いながら寝具を跳ね除けたのだった。