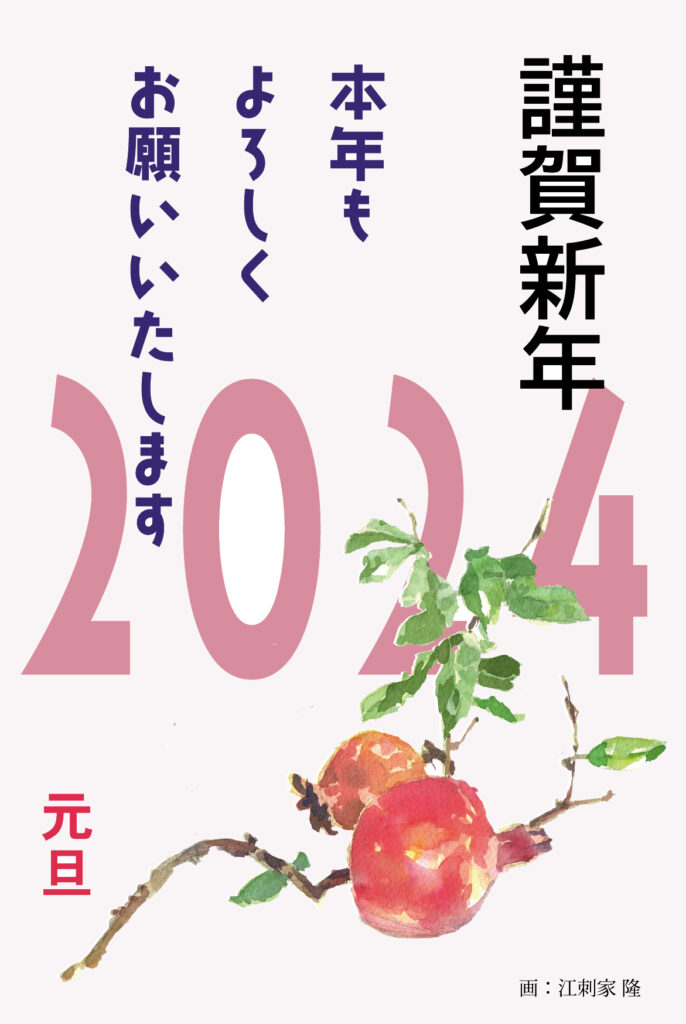
皆さん、明けましておめでとうございます。今年が皆さんにとって良い年になるようお祈り致します。わたしも、とりあえずは去年できなかったことを一歩ずつ進めていきたいと思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。
今年の元旦は、わたしの住んでいる町では少し風があるものの、比較的暖かい(最低気温2℃、最低気温12℃の予報)穏やかな晴天です。腰の具合もよく、二日酔いもしてないので、午後から今年最初の制作、撮影をしようと思っています。
昔は正月を休むのに罪悪感があって、必ず仕事をしては「正月に仕事をするなんて」としかめ面をされたものでしたが、ここ数年はすっかりジジイになって、世間並みに休むようになってしまいました。休んで悪いわけではないのですが、大事なのは自分で決めることだなあと思い直したんです。万歩計の電池も昨日でちょうどなくなり、新しいものと交換したばかり。さあ、一歩目を歩いていきますよ。
