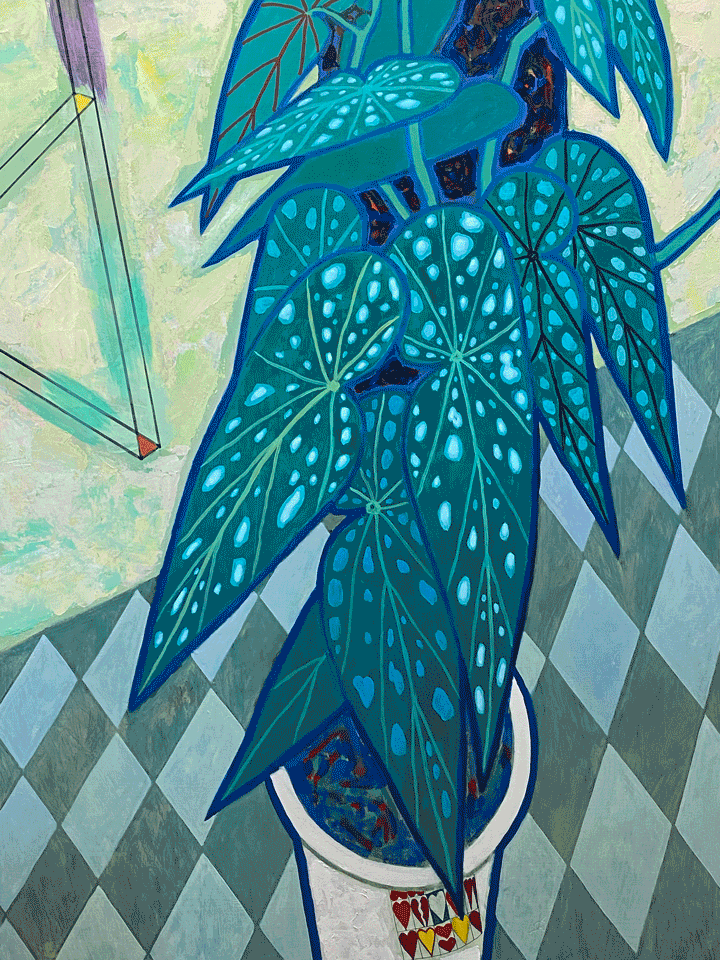それまで体調の良さを謳歌していた9月ころから、なぜか徐々に腰が痛くなり始めた。お尻や腿の裏、向う脛などに坐骨神経痛特有の痛み。10月になると、腰を真っ直ぐ伸ばせなくなる日も出てきて、ウォーキングも休みがち。そんな状況で展覧会が始まり、最終日(10月16日)には腰をかがめて画廊に辿り着く、という状況にまでなった。終わった翌日は「歩行困難」。ちょっと、無理しちゃったなあ。―終日寝ながらスケッチやエスキースをしていた。
寝ながらスケッチ?―今は誰でも寝転びながら絵を描ける時代なの―iPadなどのタブレット端末でね ― 上半身を起こすことさえできない障害者が、寝台に絵の具箱をくっつけ、家族の介助を得ながら油絵を描く映像を見たことがある。どうしても油絵具でなければならないとかいうのでなければ、現代はタブレットなどを使って絵を描くことは容易な時代になった。わたし自身も、仮にこのまま下肢がダメになっても絵を描き続けられることには全く疑いを持っていない。鉛筆1本だって絵は絵だし、ましてや色まで「寝たままで、一瞬で」塗れるとなれば。
彫刻家だって3Dプリンターを使えば作品を作れないわけではない。建築家が実物の建築をプリンターで造った例もあるし、本物の戦車をつくって路上を走り回り、逮捕された物騒なやつさえいる。テロリストグループが機関銃をプリンターでこっそり量産できる時代だ。最近3Dプリンターが話題にならなくなったのは、それがもう珍しいことでは無くなった、ということなのでしょう。文明の利器に感謝?です。
ベッドに腹這いになって描く。腰に負担はかからないが、ぶら下げる腕の使い方に慣れてないので1~2時間で肩が痛くなり、続けられない。ゴロっと反対向きになって映画を見る。見終わったら、またスケッチや絵を描く。エスキース程度なら、これまでも腰が痛い時など腹ばいでスケッチブックに描くような場面もあったが、コロナによって、そんな場面(時代)が今後日常的な姿になると確認できた。古代ギリシアでは、市民は寝たままで食事をし、寝たままで勉強、議論したようである(用事は奴隷にやってもらう)。コロナ禍前は想像もしていなかった「古代ギリシア的・プラトン(のアカデミア)的」な生活様式である(ただし、いずれにしても奴隷!はいない)。