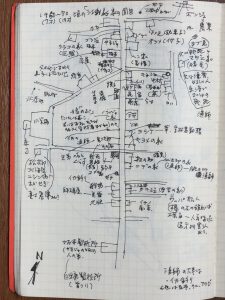今日は暖かい日だった(酷暑の続く地域の人には「暖かい」なんて皮肉かと言われそう)。25°になったかもしれない。動くと汗をかくが、室内で少し風を通すと、一枚羽織りたくなる。
キャンバスと、洋紙の10mロール2本を探していたが、とりあえずキャンバスが昨日見つかったので、急いで120号2枚張った。今日は午前中お盆用の買い物などで時間使った。疲れたので、午後からゆっくり青の下塗りを開始。夕方からはパソコンでエスキースを更に詰めようと思っていたが、少し蒸し暑いのと、ずっと続く頭痛とで何だか疲れて、夕食まで眠ってしまった。