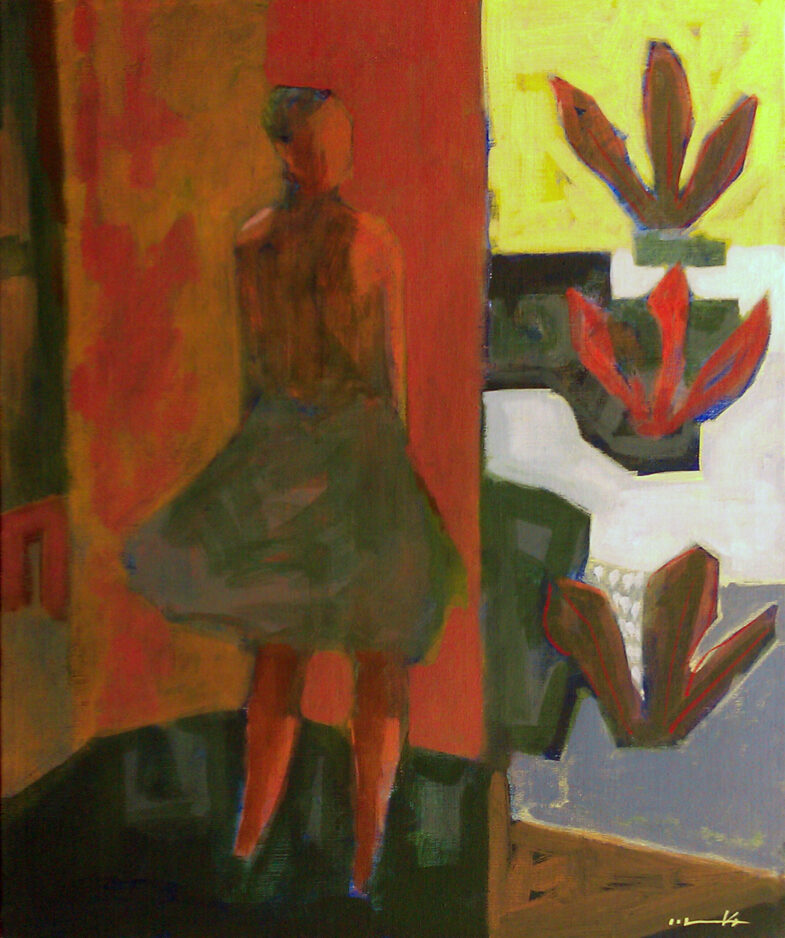「一読十笑百吸千字万歩」という、健康で長生きの秘訣をまとめた語をご存知でしょうか。毎日の健康実践目標だそうです。ご存知の方も多いと思いますが、「一読」は一日一回は内容のある文章を読む(「毎日一冊」はかなり無理)。十笑は大きな声で十回は笑うこと。百吸は深呼吸を百回、千字は文章を書くこと、アウトプットですね。日記でもいいかも知れません。万歩は文字通り1万歩くこと(最近では8000歩くらいが良いともいわれているようですが)です。出典は分かりませんが「論語」か何かでしょうか。
わたしはわりと最近になってこの語を、当時それを実践している方から教えて頂きました(現在はご高齢になり、「万歩」ができなくなっているようですが)。一つの理想論と思って聞いていましたが、それを長い間実際に続けていると聞いて仰天してしまいました。ご想像どおり、そういう人はただの人ではありません。わたしも感銘を受け、少しでも真似してみようと思ったのですが、達成できたことは一日もありません。高校生、大学生あたりならできそうな気もしますから、その頃からやっていれば、わたしももう少しマシな人になっていた「可能性」はあった「かもしれません」。
先ほどの目標のうち、意外にできそうでできないのが「十笑」と「百吸」です。笑うことと息を吸うことですから、一番自然で簡単なことのように思えるのですが、自分や家族の中に問題を抱えていたり、忙しかったりするとできないものです。この語のなかでは、意志、意識、知識に関わるのが「一読」と「千字」。「百吸、万歩」が身体、「十笑」が心に関わること、だと思います。心が閉じていれば笑うことができません(医学的にはハッハッハッハと声を出せば似たような効果があるそうですが)。
怠け者でもできそうなのが唯一「深呼吸」ではないかと思うのですが、今度は忘れてしまうのです。百回というと一気にというわけにはいきません。何回かにわけてやることになるでしょうが、忙しいとつい後回しになり、結局は忘れてしまうのです。身体に関わると分類しましたが、やっぱり心がざわついているとできません。心を平らかにしなさい、ストレスを身体から吐き出す、という訓えなんでしょうね。
わたしの実践は、その方の十分の一がせいぜいでした。それを心がけていてさえも、です。皆さんはいかがでしょうか。せめて深呼吸だけでもしよう・・そうか、深呼吸って、姿勢が悪いとできないのか・・忙しさに紛れて自分を忘れてちゃできないんだ・・立ち止まって自分をじっと見ることなんだな―・・なんて。 深呼吸って意外に深いなあ・・。