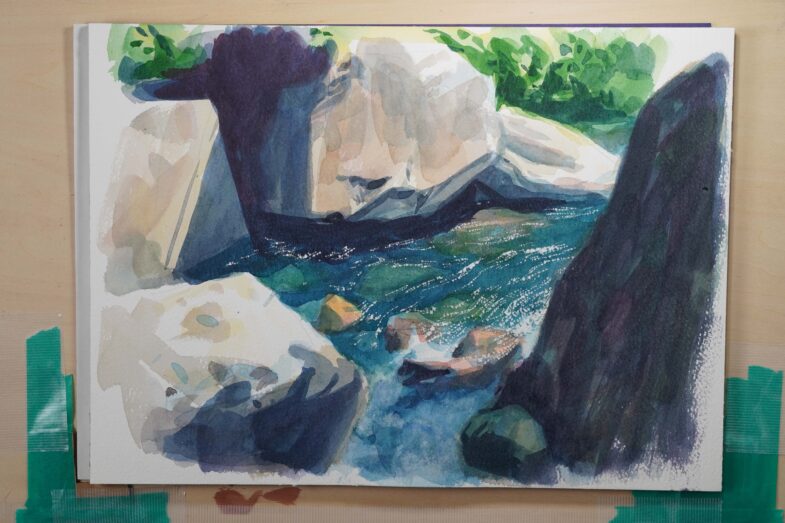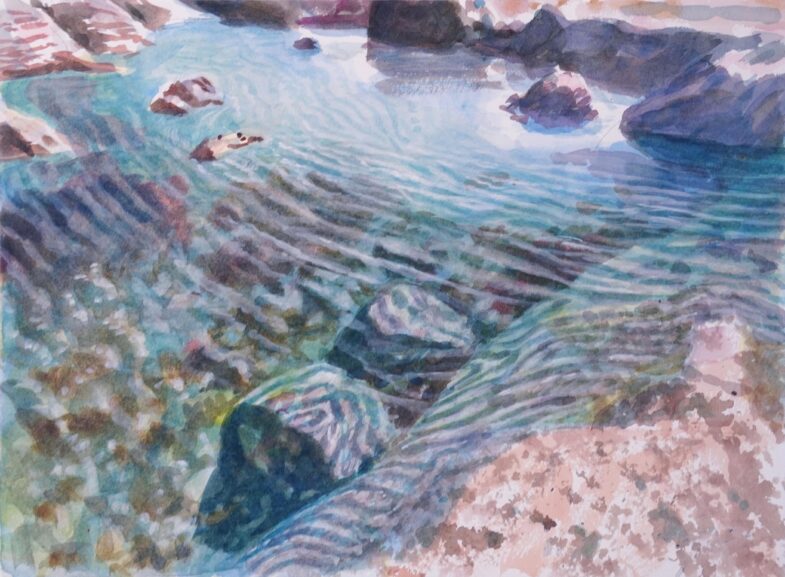写真をご覧ください。これは何でしょうか?—「らっきょう漬け」です。こんな黒いらっきょう漬けなんて、ほとんどの人は見たことないと思います。10年以上漬けたものだからです。
これ、まだ食べられるかな~?と言いながら、恐る恐る妻がガラス瓶から取り出したのは、得体の知れない真っ黒なモノ。なに、これ?—らっきょう漬け。ずっと前に作ったものだけど、食べられなかったら捨てようと思って・・。
部屋を片付けている時、隅から出てきた。記憶にはあったけれど、雑多なモノが折り重なり、積み重なって、再びその場所に辿り着くのに10年以上の時間が経ってしまった。何万㎢という広い部屋かのような言い方ですが、ごく普通の8畳間+アルファ。そのアルファに、それは忘れられてしまったかのように長い間置かれていました。
匂いを嗅いでみましたが、悪い感じはしません。それどころか、ほんのりと上品ささえ漂います。体のいい“毒見” なのですが、箸で触ったとたん、滑らかに箸の先が沈んでいく―こ、これはスゴイかもしれない―ねっとりした触感と、絶妙の深い味わいでした。「これ、すごいよ、絶品!」と思わず叫んでしまいました。酢漬けの奥深さにもあらためて感動です。
普通の砂糖の砂糖の代わりに、沖縄の「黒糖」を使ったとのこと。唐辛子もちょっと入れたらしいのですが辛みは感じません。らっきょう漬けと言えば新鮮なシャキシャキ感が魅力ですが、それとこの触感はおなじ素材からとは想像できないほど違います。「もっと作って」と言いたいところですが、これを作ったのは妻ではなく、本当は「時間という魔術」。今から10年後では(もしかしたら5年でも、3年でもいいのかもしれませんが)、生きているうちに味わうことができるかどうか、微妙です。でも、ヨカッター、とりあえずこれを味わえて、と本当に思いました。
皆さん、もしも古い酢漬けが残ってしまったら、捨てる覚悟であと2~3年保存してみたらいかがでしょう。魔法が現れるかも知れませんよ。