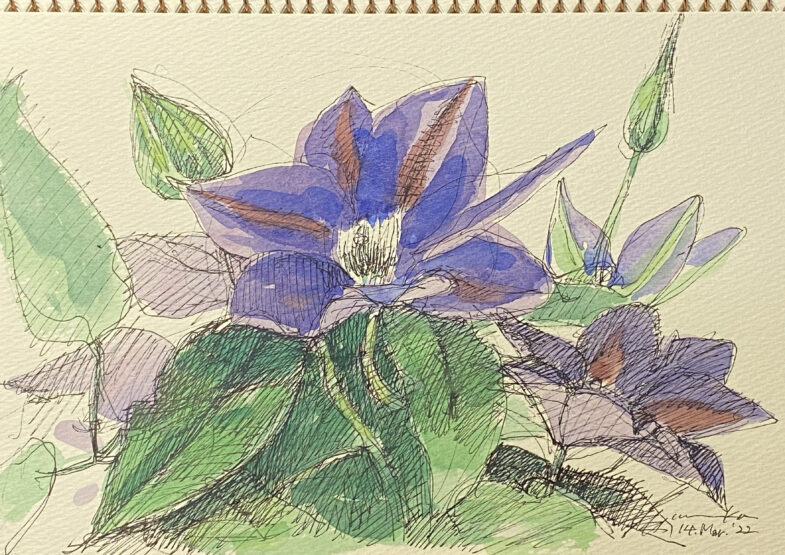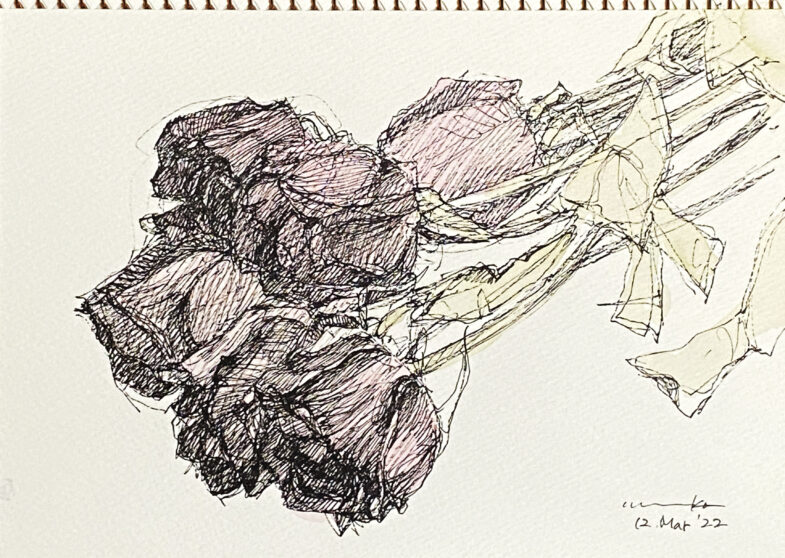
ウクライナへのロシア軍侵攻には、多くの人が心を痛めているに違いない(その逆も半数は居る、と考えるのが「世界の常識」らしいが)。その中で、黒海沿いの主要港湾都市マリウポリにあるアゾフスターリ鉄鋼団地に、圧倒的な戦力のロシア軍に対して立てこもるアゾフ大隊・ウクライナ軍が昨(5/16)夜「任務を終了」し、傷病兵を含め、ロシア側地域にではあるが、一部投降、移送されたとのニュースに、人道的な意味でホッとした人も少なくはなかったと思う。
ウクライナのゼレンスキー大統領(もうそのプロフィールを書く必要はあるまい)にとって、ある意味では苦渋の決断ではあっただろうが、素人目にもよく計算された、最善の決断だと思う。太平洋戦争における日本帝国軍の「玉砕」戦法(戦法といえるかどうかは別として)に比べても、2021年9月のアフガニスタンにおけるバイデン大統領の撤退期日公表に比べても、あらゆる意味で一段階上の合理的、冷静な判断だった。
2/24未明のロシア軍の侵攻直後、ウクライナは一気に対空防御能力を失った、と思われた。その後の一方的な空爆により、「外交知らず」「戦争知らず」「政治的無知」なはずの、「コメディアンあがりの」(たまたま大統領になってしまった)ゼレンスキーは震えあがって国外に逃亡し、アメリカが用意したベッドの上で口先の「亡命政府」を名乗るだけになる、と多くの人が予想したが、彼はそうしなかった。どころか、それらの予想を180度ひっくり返して見せている。5/17現在で、ウクライナがなお領土防衛の高い士気を保っているのは、ひとえに彼のこの姿勢が原点になった、といっても過言ではない。
まさに映画のヒーローそのものであり、ゼレンスキー氏自身が当の映画人であってみれば、「彼が(たまたま)大統領に選ばれた映画」そのものをいまだに演じ続けていて、おそらく心の奥底で、彼の役者魂がかえって彼を真の大統領に為しえている、とわたしは想像する。彼の冷静さも自分と役柄との微妙な呼吸から。どこかで自分自身をカメラで追っている感覚。それが彼を本物のヒーローにしている、ひとつの力なのではないだろうか。