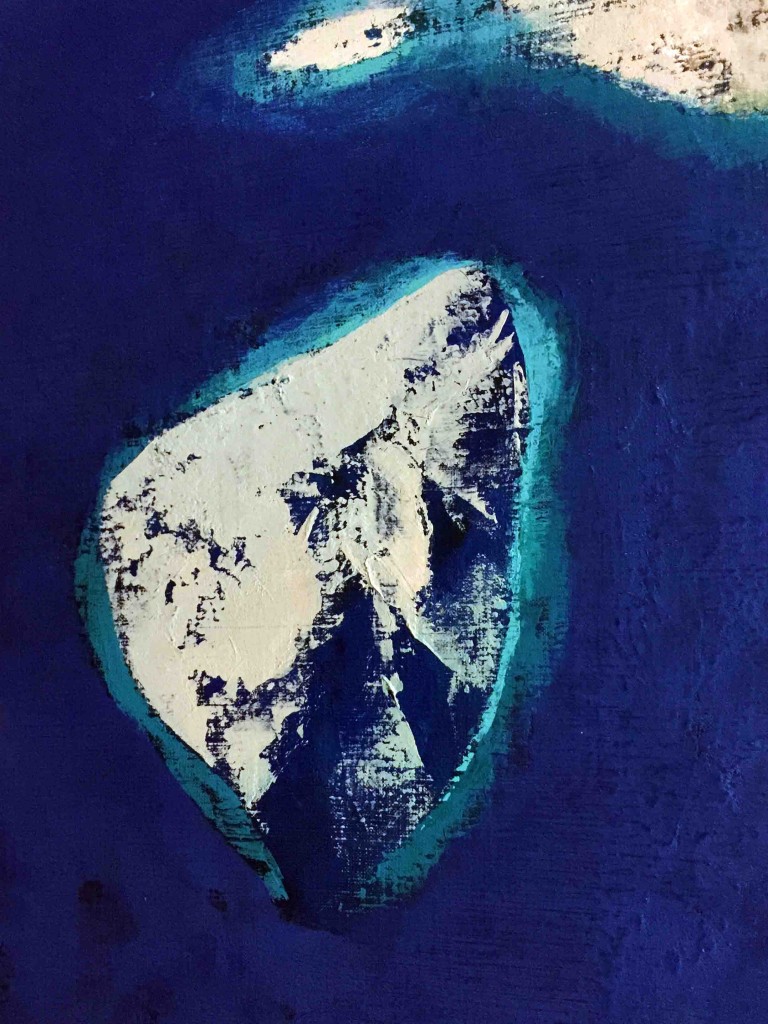※これは架空のお話です。
一度教室をやめて、また戻ってきました。
特にやめる理由も無かったように、はっきりした理由があって戻ったわけでもありません。強いて言うなら、クラスの人に戻って来なよと誘われた(再勧誘?)からですが、理由になりませんよね。
教室には10年間通いました。ほぼ無欠席。結構大きな絵も描いたんですよ。でも、コンクールなどには出しませんでした。先生も特に出せとも言わなかったし。自分としては少しは出したい気もありましたが、積極的でもなかった。いえ、それが不満だったんじゃありません。でも、なんとなく、少しずつ風船から空気が抜けていくように、すうっと気持ちがなくなったんです。
体力はありますよ。元気、元気。教室をやめても絵を描く気持ちはあったんですが、ここがなあ、とか言われないと張り合いがないというか。10年間の惰性なんでしょうか。
絵を描かないと、アイデアが浮かぶ。描いてる時は、目の前の処理で手一杯。考えられないんですよね。で、アイデアが浮かぶと描きたくなる。描き始めると、できないところ、ダメなところが案外すぐ分かっちゃうんですよ、自分でも。でも、どうしたらいいかが分からない。それを放っておけないんですよね、性格っていうのか。
だから戻って来たってわけじゃないんですよ。なんとなくね。でも、今度はコンクール出してみようかなと思ってます。入選とか賞とかの欲があるわけじゃないけど、ちょっと頑張ってみようかなと。でも、入選したら案外もっと上の欲が出てくるかも、ハハハ。