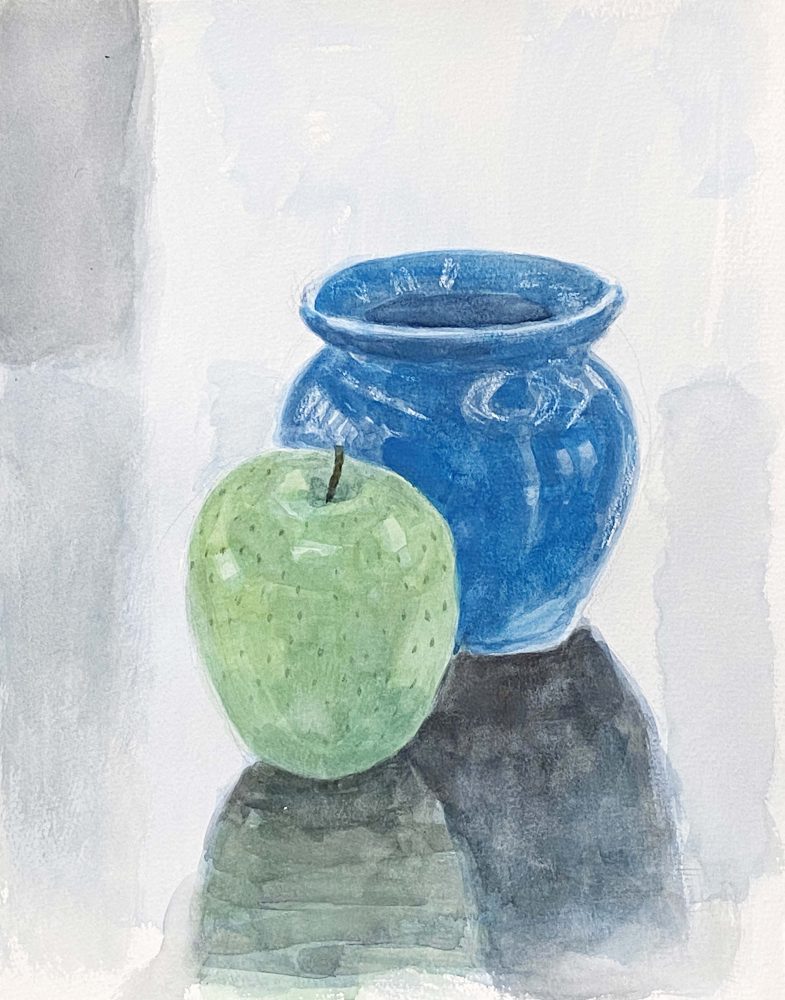新型コロナ・ウィルス(Covid-19)がヨーロッパと南北アメリカ大陸、さらにオーストラリア、アフリカへと広がりつつある。アジアでは中国と韓国がどうやらピークを越えたようで、台湾、シンガポールが制圧に成功するかどうかの瀬戸際。他のアジア諸国では日本同様、感染が拡大しつつあるというのが大勢のようだ。ウィルスの国内感染を防ぎたいのは世界各国共通だし、入国制限などの具体例では日本もほぼ各国と横並びだが、そのプロセスにおいて日本は世界と考え方が全然違う国なのだな、とつくづく感じさせられた。
安倍首相は「専門家の助言を聞いては『いないが』」(自分自身の判断だ)と述べるのに対し、私の見る範囲内に限るが、各国の首相、大統領は「専門家の意見を(常に)聞きながら」と、「専門的・科学的知見を前提に」国民に訴える姿勢が極めて対照的だ。確かに、思い起こしてみれば「私(安倍)は『森羅万象を統括する』総理大臣でありますから…」と国会答弁で幾度か堂々と応えているから、そういう姿勢もなるほどとはうなづける。「森羅万象を統括できるならそもそもcovid-19など出すな」とは誰しも思うけれど、虚言癖、誇大妄想、記憶喪失という重い症状だといわれる首相の言葉などに、いまさらこだわっても時間の無駄だ。
けれど、安倍氏をナメてはいけない。彼は政治の「天才」だと、私は思う。ヒトラーに極めて近い人間性を持っていると私は感じている。天才はたいてい「純心」だ。「純心」とは、自分だけがこっそり儲かるような行動をするとか、そんな世間的な打算が無いことをいう(選挙は別)。祖父の岸信介の願望達成に命を懸ける純心さ(皆のためになると思い込む宗教心に近いもの)、それが、元々ポリシーなどなにも無い多くの単純・無心(≠無垢)な自民党議員をまとめる力にもなるのだろうし、「特攻精神」などを崇高と賛美する一部国民の軍国主義的な美学(宗教)を代表できるのだとも思う(念のため断っておくが、旧日本軍における特攻隊隊員がそのような単純な精神の持ち主だけだったなどとは、私は露ほども考えていない。むしろ「特攻精神」なるものは特攻せずに済む人々による、単に煽動的な言葉だと考えている)。
そのような美学(宗教)を共有する人々には、日本を「ヤマト民族」独自の「当たって砕けろ」の特攻精神だけでcovid-19にぶつけ、しかも「必勝する」という信仰があるのだろう。科学的裏づけを二の次にしたがる、そうした神がかり的な発想が「いさぎよい」犠牲を国民に強い、そのあとを「自己責任」と丸投げする安易さにつながっているのではないか。