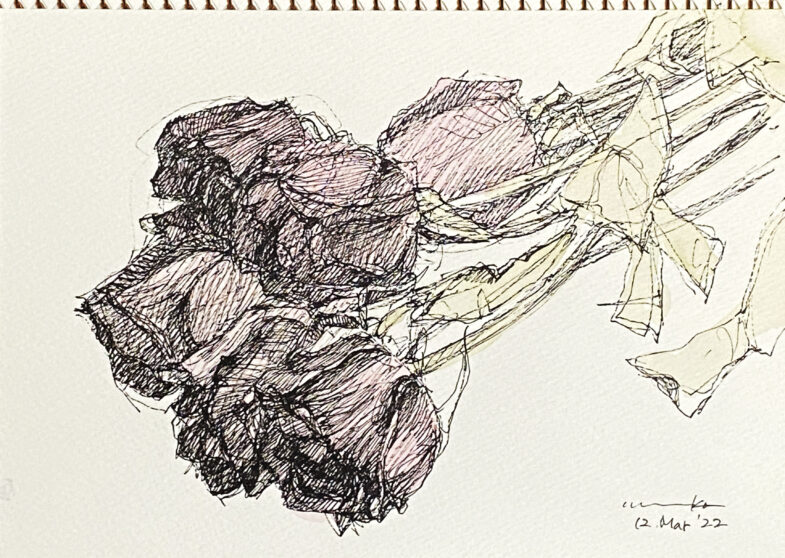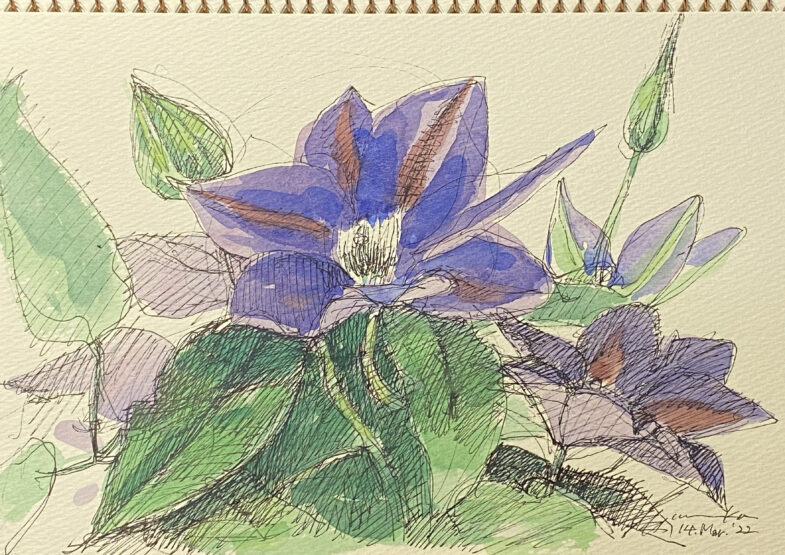「ヴォドゴルコフ伍長はウラジーミル軍曹との戦闘を再開した。会ったことはないがお互いに顔どころか、趣味や、ある程度の生活の状況までよく知っていた。互いの距離は100km。もちろん銃などの届く距離ではないが、目まぐるしく位置を変える相手のうしろ姿を、獲物の匂いを嗅ぎつけた犬のように追っていた。
ヴォドゴルコフ伍長は80歳になったばかり。ウラジーミル軍曹は数年前にすでに亡くなった。けれど、今はどちらも24歳。どちらも上空のドローンに見つからないよう、なるべく葉の多い木々の下を選び、腰を屈めながらネズミのように小走りする。」
「ヴォドゴルコフ伍長は病院のベッドでたくさんの医療用チューブに繋がれたまま、ゲーム機のようなボタンに指を置いている。ウラジーミルは、禿げた頭と真っ白いあご髭を振り回しながら、楽しそうに24歳の頃の思い出をモニターの中で語っている。背後のモニターでは若い彼がキーボードをたたきまくっている」―これは仮想?いや、どちらかが引き金を引けば(ボタンを押せば)実際に弾が発射され、そこでどちらかか、あるいは他の誰かが死ぬ―VRで戦争すればこんなふうになるのだろうか。
VRで戦争すれば―と書いたが、1990年の湾岸戦争で、わたしはすでにVRでの戦争を見た。モニター上で破壊される戦車は虚像であるが、数キロ先で実際に戦車は破壊され、若い兵士がその中で体を引き裂かれて死んでいる。いま現実に起きているウクライナでの戦いはすでにVR戦争そのものだ。
※VRは「Virtual Reality / バーチャル・リアリティ(仮想現実)」と訳されるが、Virtual という語には「仮想」というより、むしろ「現実的・実質的な」という意味合いが強く、「見かけはそうでなくても、こちらが本当(現実)でしょ?」という内容を示している。
わたしはコロナウィルスがどんな形をしているのか、生理的な視覚では見ることができない。けれど、その姿を知っているどころか、疑うことさえしない。知床の観光船が海底に横たわっている姿も、それが現実だと信じて疑わない。カメラが出現したときから、いや、実際は人類が「絵画」を創造したときから、現在のVRまでは歴史の必然だったとさえ思える。朝、食事をする。ご飯、パンを食べているのか?それとも目に見えないはずのカロリー、タンパク質何グラム、を「食べて」いるのか?計算通りダイエットが進めば、それが「現実」?