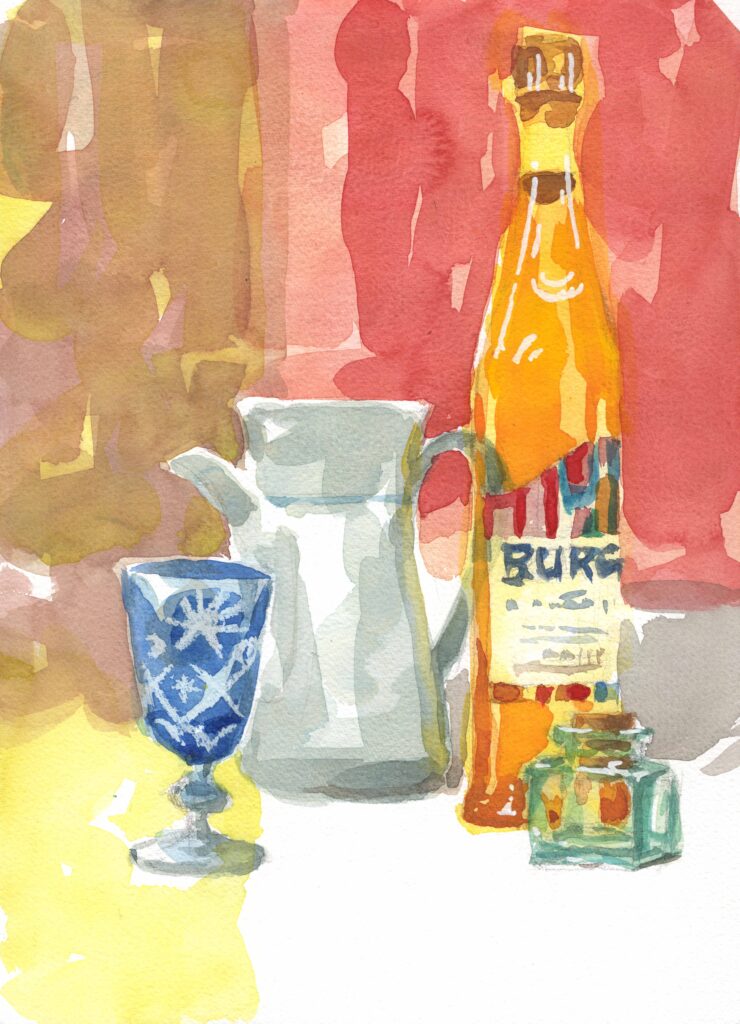かつて世界選手権やオリンピックの代表だった、某スポーツ・コメンテーターが最近こんなことを言っていた。「スポーツ界が、スポーツをやらない人の税金まで使って、社会に何を還元できるのか。それを考えないと国民がスポーツから離れて行ってしまう」。
心情を理解できなくはないが、ちょっと危ないなと感じるのは「税金を使うのだから何かを返さないと(いけない)」という、ギブアンドテイクに似た部分。この部分は最近の日本ではむしろ多くの人に共感されそうだが、少し深く考えれば「返せない(と思われる)人には使わせない」という社会的弱者の排除につながりかねず、子どもの教育にも、「将来国に返せよ」という国家主義的な義務感を植え付けかねない、と思う。もちろん本人は直接そんなことは言っていないが、そう解釈されそうな論理を孕んでいる。この「返し」が「かたちあるもの」になってくると「(金)メダルでないと意味がない」などという発言になってしまう。
そんな考え方をしてしまうと「では、芸術は何を返すのか」ということになり、かつてのロシアや現代の北朝鮮のような「国家に奉仕する」プロパガンダ絵画になる。「芸術は社会のカナリアだ」という人々がいる。確か、むかし炭鉱夫が坑内へ入るとき、酸欠状態かどうかを知るためにカナリアを先に入れたということが言葉の起源だったと記憶している。スポーツや芸術を認める社会がとりあえずは「安全」だ、というバロメーターとしてだけでも、すでに充分意味のあることだ。
世は健康志向だ。けれど、三流映画に出てくるような、ただただ殺戮するだけのロボット的な軍人ならともかく、運動と栄養だけで人間は健康になれるわけではない。精神的な愉しみ、安らぎが必要だ。心の栄養も不可欠だということ。人間らしさ、という意味では芸術は最も社会還元の大きな分野だ、とわたしはいつも思っているが、同時にそれがこの社会の常識であり続けることを、心から祈ってもいる。