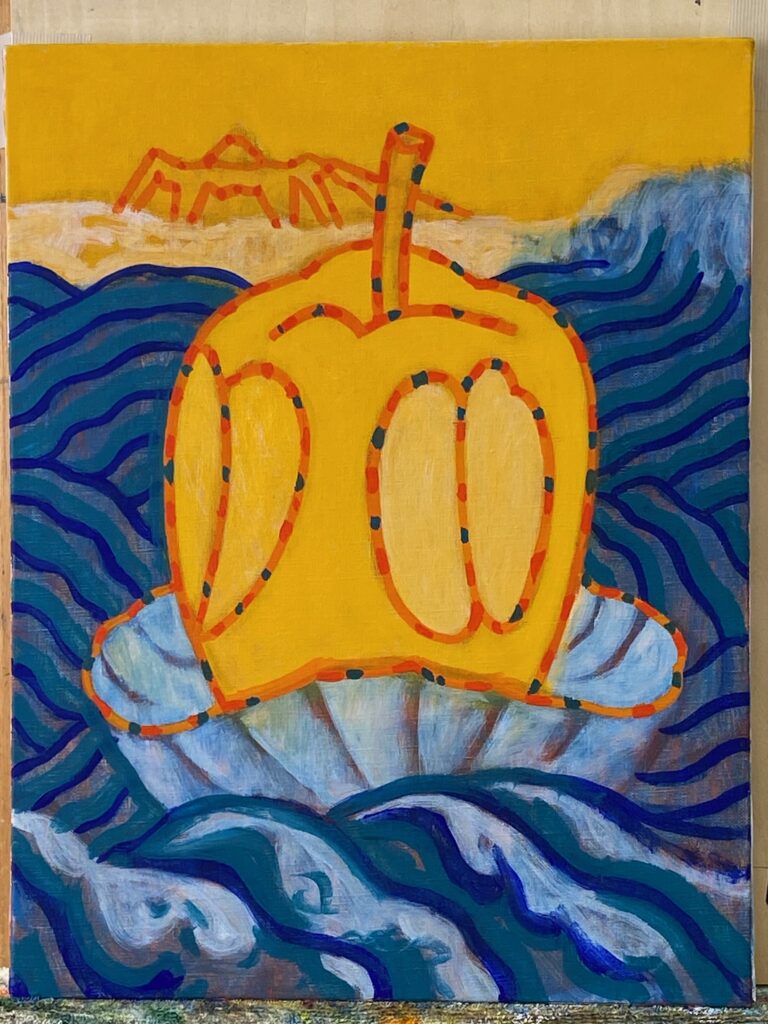同じ紫陽花(あじさい)の試作の中から3枚掲示してみる。仮に上から順に1、2、3と呼ぶことにするが、描き方は少しずつ異なっている。3枚とも同じ用紙、同じ光線条件で写真を撮っているはずなのに、なぜか1枚目だけ紙の色が違う。当然、花の色も2,3とは変わっているはず。どうしてでしょうね。
1はデッサン主体。2は色彩主体、というよりほとんどデッサンがない。3はほぼその中間。こうやってみると最も「絵画的」とわたしが感じるのは2。アジサイという「植物種」から離れて、色(明暗を含む)とかたちだけの「造形本位」の度合いが強いから。並べているからアジサイだと推測されるけれど、2を単独で見たらアジサイと認められるかどうかは半々だろう。もう一歩押せば、もう誰もすぐにアジサイとは判定できなくなる。
これはわたしの(いま現在の)感じ方であって、見る人はそれぞれ勝手に感じればよい。ただ、その場合でも、先に述べたような(1はデッサン・・のような)分析的な区別はしなければならない(その分析的なファクターは個人個人が自由に設定してよい)。なぜなら、それが「ものの見方」そのものだからだ。そのファクターが独創的であるほど、ユニークな視点(分析力)を持っているということだと思う。この場合は個人個人のフィルターと言っても、フルイ(篩)でも、色眼鏡と言い換えても内容は変わらない。
同じモチーフを、たとえばこんなふうに表現を変えて制作してみることは、絵画の質を深める有効なプロセスになる。表現(法)ではなく、アイデアの方を変えることも昔からよく行われている(絵画では変相・ヴァリエーションと言われるのがそれ。音楽の「変奏」も同じ意味ではないだろうか)。
絵画ではモチーフ本位の「何を描くか」と、コンセプト・表現本位の「どう描くか」の論争がかつてあった(らしい)。わたしはそのあとの世代だが、その時代のコンセプトとは別に、若い頃は「何を描くか=テーマ」が大事だと思っていた。当時は絵画が社会的メッセージとしての力をまだ持っていると思っていたから。
今は?―わたしは「絵画の歴史的生命」はすでに尽きた、と考えている。けれど同時に、絵画はまだまだ終わらないとも思っている(残光?)。説明は省略するが、そこが人間とAIまたはロボットとの違いだと思っているから、とだけ言っておこうかな。