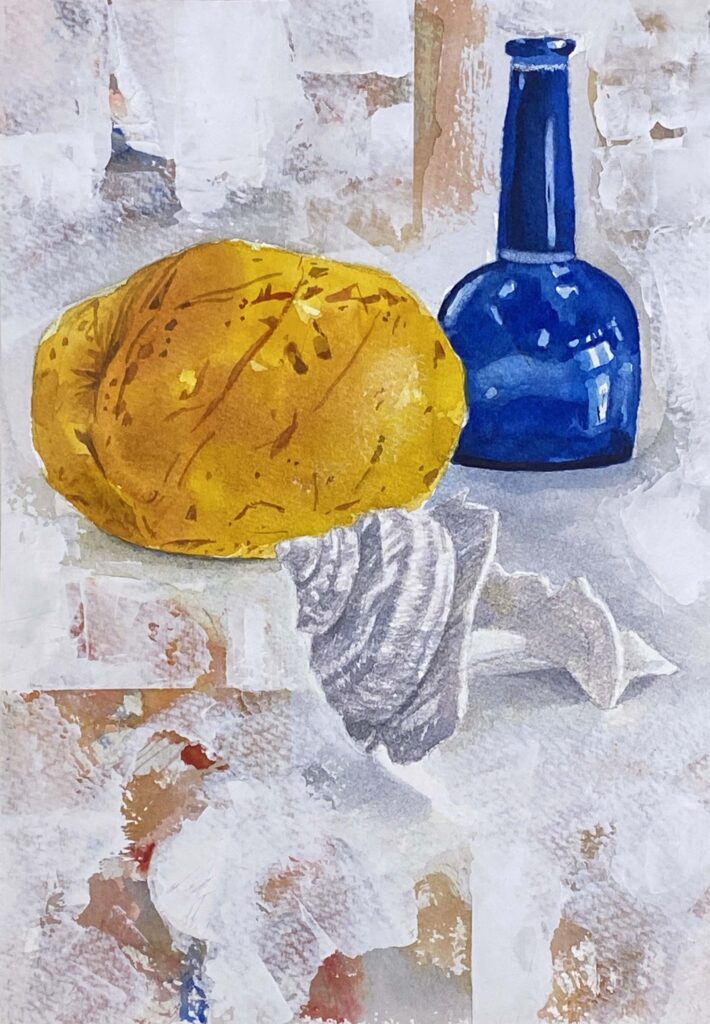懸案のビデオやっとアップできました。前回のアップ後一週間は、ビデオ関連のことは何もできなかったので、実質10日間編集にかかったことになる。特に3連休はまるまるこの編集のために消費してしまった。
ビデオのために絵を描く時間は、水彩の場合、長くても2時間。たいていは1時間ちょっとで終わる。描きながら喋ることができれば、ナレーションなど考える時間はほとんど不要だから、カット編集だけで一日あればできるかもしれない。そうすれば週1回はもちろん、2、3回というアップ頻度も可能にはなる計算だ。
でも、喋りながら描くということは、現実的ではない。まあ、デモンストレーションでは、部分的にややそれに近いことはできるが、下描きから完成までずっと喋っていたら、集中できず、絵の方ができなくなってしまう。ここ2作ほどは、ずっと喋りつづけているが、そうした方がいい、というアドバイスに従ってやってみている。ナレーションの言葉を考える時間は膨大だし、何より「絵を描くのに、こんなに言葉が必要なのか?」という疑問を拭い去れないままに喋りつづけている。しかも、1.5倍速を目指して、早口に。当然、楽しいはずもない。そもそも、自分が描きたい絵を描いているわけではなく、ビデオのための絵を描いているのだから、それに合わせるのは仕方ないことだろうけれど。
どうせビデオを作るなら、作っている自分も楽しめる方がいい。ストレスも減るし、モチベーションも維持できるし、なにより健康的だ。理想を言えば、誰かが、わたしが描いているビデオを作ってくれるのが一番いい。その出来具合に、時どき茶々を入れて笑い合うのがいい。そんな日がいつか来るんだろうか。