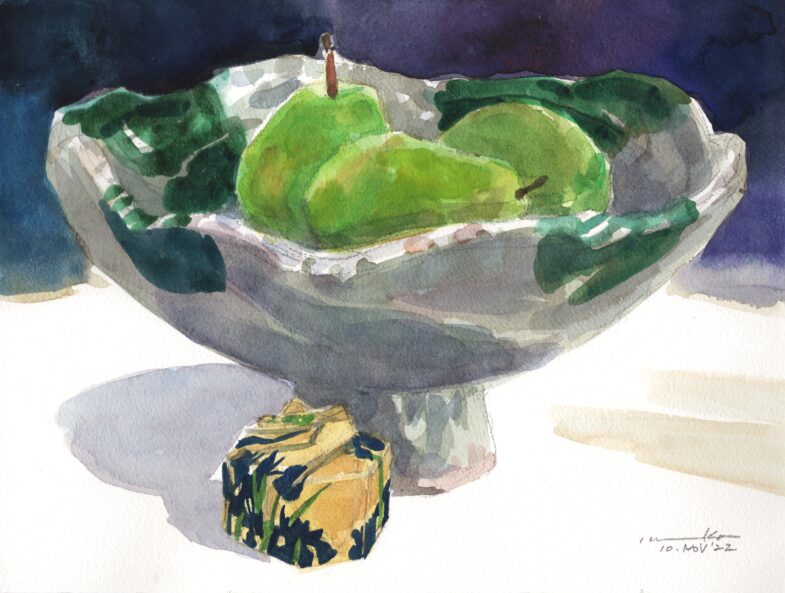「もうお金がないよ」と妻に言われるとドキッとする、どころか急に息が苦しくなり、心臓のリズムも乱れ眩暈がする。
そう言われても無いものは無いのだから仕方がない。「困ったね」と、コーヒーをこぼさないようにしながら、とりあえずそそくさとその場を離れるしか選択の余地はない。いったい誰がお金などと言う無粋なものを発明したのか、などと恨んでもはじまらない。
お金という概念の存在しないところで、一人で、魚を釣ったり、適当に畑を作って何か口にしながら好きなことをするのがいいな。そしてある日どこかで倒れたままあの世へ行く―無人島で一人で暮らす、といえばデフォーの「ロビンソンクルーソー漂流記」を思い出すが、漂流する直前までの彼はそこそこの貿易商人で、れっきとした経済合理主義者である。その本をネタにした経済学の研究や本もたくさんある。ドローンでどこにでも商品が届くようになると、狂人になるか深海の底にでも潜る以外、お金というものから逃れるすべはなさそうに思える(水中ドローンというのも急速進化中だから、深海底でも油断はできない)。
「もうお金がないよ」と何度言われても、その恐ろしい響きに慣れることができない。そのたびに息が苦しくなるが、やっぱり現代に生きている以上、慣れてはいけない言葉だとも思う。そのつど心臓を傷めるが、お金のストレスによる眩暈にペースメーカーは無力である。お金という特効薬以外に効く薬も無さそうなのである。