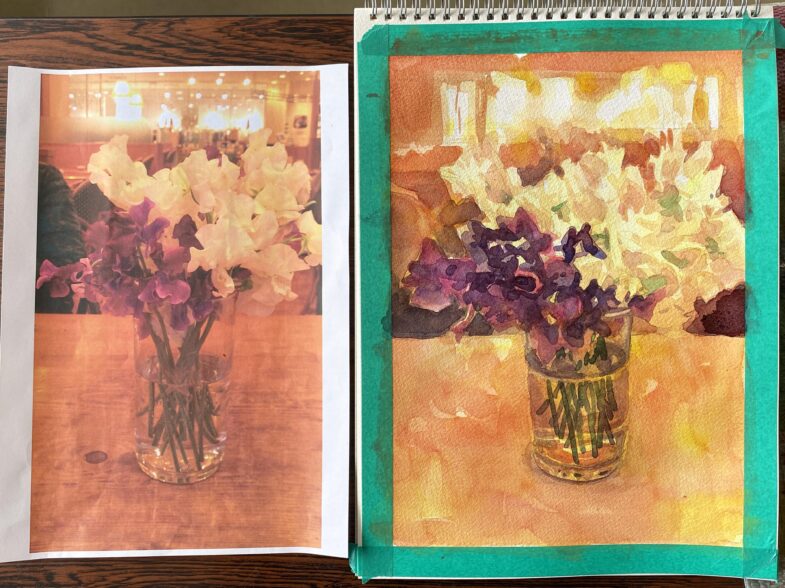―あなたは今日、何をしていますか、またはしましたか?―
何でもない質問のようですが、時にはされたくない質問ですよね。思わず、“ボーっとしてちゃ悪いんかい!”と投げ返したくなる時もあるんじゃないでしょうか。「今日の予定はもうありません」も、スマートフォンに表示されるたびに「だから、なに?」でした。
なぜだか、わたしはものの「切り口」を見るのが好きなようです。リンゴを齧ると、皮の切り口から中身が見えますね。そういう状況、状態を見るのが好きなんです。何時間も見ていて飽きないのです。でも、それじゃ食事が進まないので、現実にはむしゃむしゃと食べてしまうのですが。
彫刻家が木材を鑿で掬うときの鑿の跡。鑿が木材に入り込む角度、早さ。刃先の鋭さと木材の柔らかさとの絶妙のタイミング、つまり「技」を、頭の中で超スローモーションで想像・再生し、修整・編集し直して、納得して初めて、「この目で見た」という気持になれます。わたしは彫刻家ではないので、わたしのいわば「脳内ビデオ」が正しいかどうかは判りません。彫刻家自身からのサジェスチョンがあれば、それをもとに再修正することになりますが、そこに自分のピントが合わない限り、「見た」という気分にはなれません。
そうやってすべて、ひとつひとつ自分の感覚の中に落とし込んでいくことが、わたしにとって「ものを視る」という意味のようです。そして、その最も解りやすい場所、それがどうやら「切り口」ということらしいんです。けれど、それはけっしてわたしだけの特別な視点でもなさそうです。時代劇映画などで侍が人を斬る。その切り口を検視すれば、どれほどの使い手か判る、などというかなり専門的な設定でさえ、誰もが疑問を感じずに映画に興じることができます。わたしの視点は、むしろとても常識的なものだということになるでしょう。
けれど、通り一遍の“ざっと見”では無理です。映画の中だって、深く「じっと見る」はずです。じっと見ている=何もしていない、じっと考えている=何もしていない、という等式が「あなたは今日、何を・・」の質問から感じられるとき、一つの断絶がその切り口を見せているんだな、と思うのです。