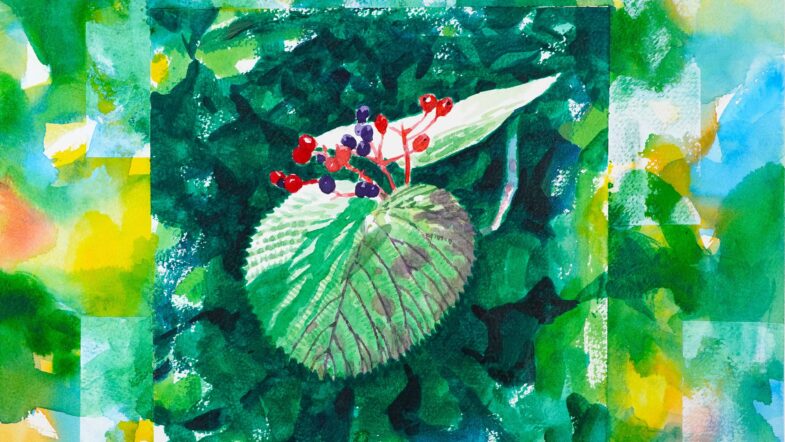いよいよ絵を描かなくっちゃならない。義務ではない。仕事でもない。自分の人生としての、まとめとして絵を描かなくっちゃならないんです。
今までもたくさん絵を描いてきたし、今も描いてはいるのですが、どうも「自分の絵を描いた」って感じがしないんです。このままじゃ、自分の絵を描かないまま、あの世行きだなー、なんて考えるトシになってきたんです。自分をフジミ(富士見×、不死身〇)だと信じていたこのワタシが、ですよ。
じゃあ、これまでの絵は何だったの?ってことになりますよね。“かなり手前味噌” になりますが、これまでだって、「他人の絵」を描いてきたわけじゃあないはずだし、いま自作を見ても、自分の世界観がそれなりに絵の中に込められているとは思います(これを「独りよがり」というのでしょうが)。でも、何か足りないんです。
良い絵を描きたい、というのとは違います。「良い絵」が描けたと自分が思っている時が、一番ダメな絵を描いている時だ、ってのは、これまでの人生で深~く味わってきたから、そんな次元はもう卒業しました。願うのは、「自分にもこんな世界があったんだ」or 「もうこれ以上は無理だぜ」ってヤツかな。
それを描いた直後に死ぬってのはまるで時代劇ですが、アイツは昔の人だからと、そこは大目に見てもらって、「この人があと数年生きていたら、もっと面白い絵を描いただろうなー」と、想像したくなるような絵を描いて死にたいんです。べつに、そういう評価が欲しいわけではありません。そう思えるような絵を描きたいという気持、あの世へ持っていきたい一枚ですね。