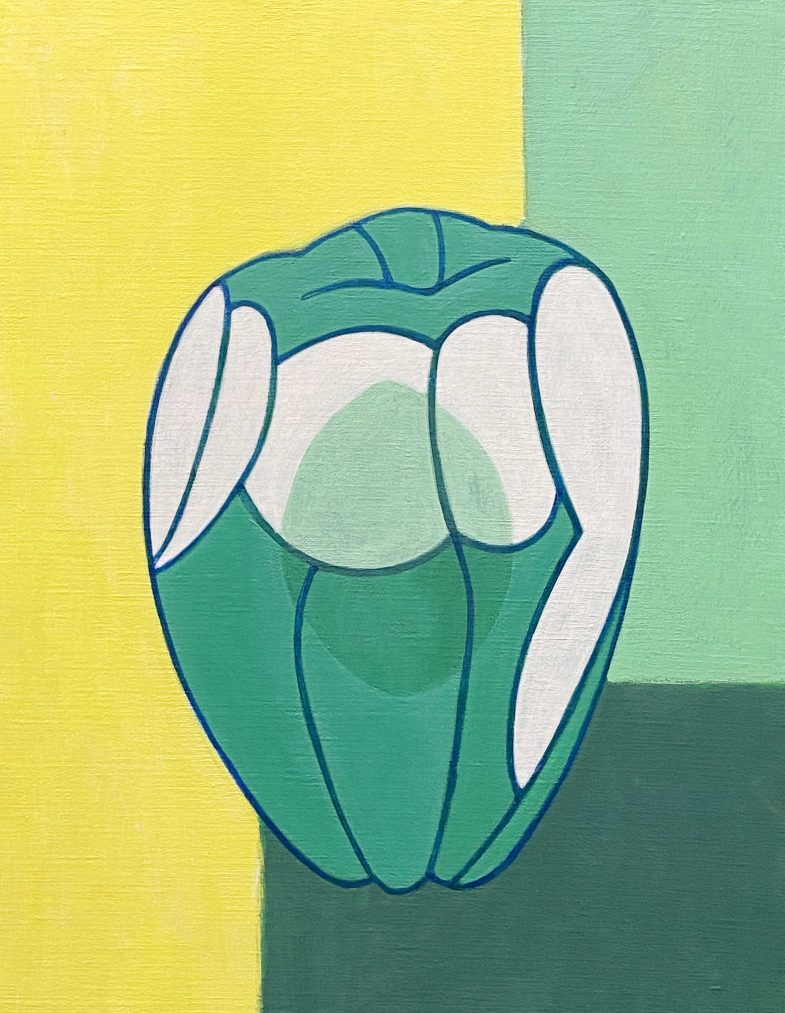
現在、世界のおよそ3分の一にあたる人々に、移動の制限がされているらしい。Covid-19が猛威をふるうヨーロッパでも、犬を散歩させる場合でも自宅から10m以内という厳しい制限のあるところもあれば、庭や公園で友人たちと食事を楽しんだり、スポーツなど身体接触があっても(全体として気をつければ)OKというレベルの国、地域もある。みんながみんなパニックになっているわけではない。
外出制限、テレワーク(自宅でのパソコンによる仕事)、休校、レストランなど生活必需品の販売以外の商店の閉鎖、三人とか五人以上の集会禁止、ほぼあらゆるイベントの中止、美術館・博物館・図書館・劇場などの文化施設の休館…など、要するに強制的に自宅で休みを取れということ。普通のときと違うのは、いつ休みが終わるのかわからないということ。そして、長引きそうだということ。
アメリカ・エール大学のインターネット通信講座の受講者が50万人増えたという。この機会に、新しい資格を取るための勉強を始めたなどというポジティブなニュースが、スマホやパソコンの画面を駆け巡る。「不安がっていても仕方がない。お前も前向きに何かためになることをやれ(文句をいうヒマがあったら)」と圧力をかけられているような気がして、かえってストレスだ。ポジティブも結構だが、ただ体を休めるだけだって悪いことじゃないだろう。
海上で遭難し、ゴムボートなどで漂流する時、早く死ぬ人は体力の消耗より、先が見えないことのストレスによる方が多い、という話をどこかで聞いたことがある。だいぶ昔のことだから、今もそれが事実なのかはわからない。でも、先の見えないのが大きなストレスになることは確かだ。気を紛らす術を知っている方が絶対にいい。図書館から100冊くらい借りておけばよかったが(実際は10冊までしか借りられないが)、真っ先に休館されたのは残念だった。

