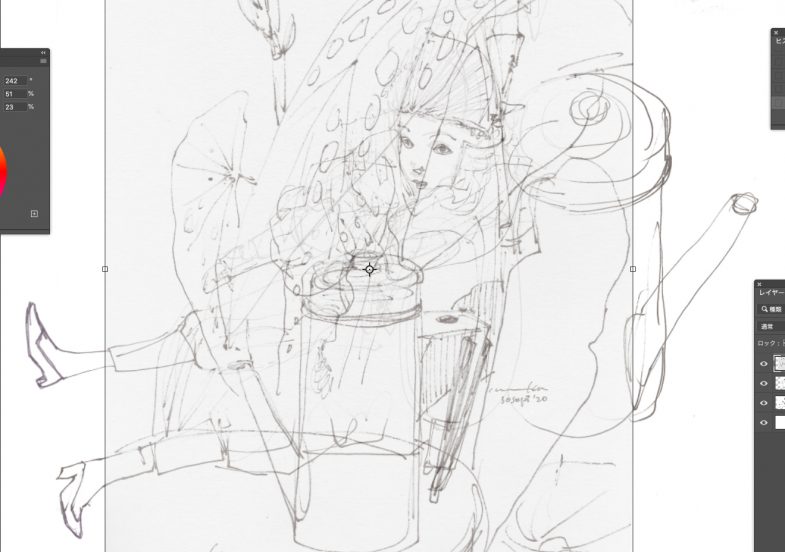
「世の中は一歩出れば全て競争だ」「だから子どもたちにもできるだけ早くから、それに対応できる力をつけさせなければいけない」、と多くの人たちは考えているようだ。学力しかり、経済観念しかり。そのために学校へ行き、そのために勉強し、そのために良い大学へいき、良い会社に就職する。そこまでの競争を勝ち抜けたことに感謝し、その競争社会のために奉仕する。それが「子供たちの将来あるべき姿」だと、考えているようだ。
新総理大臣の「自助(自分のことは自分でやれ)」「共助(本人ができなければ家族、親類等でカバーしろ)」「公助(あきらめて死ぬ覚悟くらいはさせてやる?)」に、世論調査で70%近い支持を示す国だから、それに疑問を唱えたって、まともに相手にもされないだろう。要するに「競争を勝ち抜けば〇」と言っているわけで、「なんだかんだ言っても、金がなければ何もできない」という「常識」も同じ発想から来る。
TVの中で、ある小学校では「努力して、以前より少しでも順位を上げる、その過程、頑張りを評価するのです」と校長先生が、いかにも順位本位ではないというふうに胸を張る。けれど3位の子が1位になれば、1位の子は下がらなければならない。その子は努力をしなかったという評価になるのだろうか。
「その悔しさをバネにして、次回は頑張れ」というなら、次には今1位の人を引き摺り下ろせという意味であり、これでは単に苦しみを繰り返すばかりの地獄ではないのだろうか。そして、それが本当に「本人のため」なのだろうか。いつもビリになる子に、どんな「肯定的評価」があり得るのだろうか。そしてこれは、別に子どもや特定の分野だけに限ったことではない。要するに「勝ち組」以外をふるい落とすための「国民的制度」に他ならない。
その「常識」は、どうやら世界の隅々まで、というのではないらしい。「競争だけが人生だ」とか、「倍返し」などという言葉とは遠い国々がある。世界で最も「幸福度」の高い国々だ(「世界幸福度報告:国連の持続可能開発ソリューションネットワークが発行はする幸福度調査のレポート。自分の幸福度を10段階で答える世論調査の平均値)。国の経済力の大きさと国民の幸福度とは一致しない。人を引きずりおろしてその地位を奪う。その瞬間だけは幸福度が高いかもしれないが、その逆の場合に、幸福を感じる人はいまい。競争をすべて否定するつもりなどないが、勝ち負けにもっとも高い価値観を置く気持は、私にはない。

