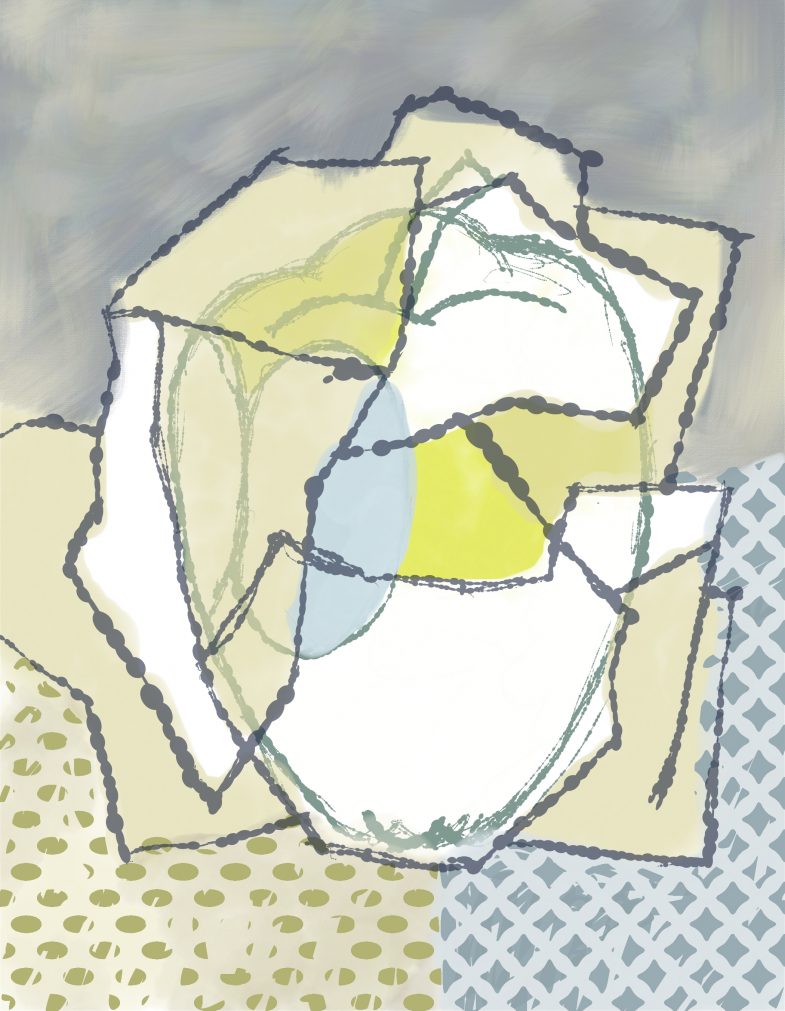上の絵は写真をもとに、ペンブラシというソフトで描いた。イラストなどを描く人の誰もがやる、初歩中の初歩のCG。誰でもやるが、誰が描いてもおなじになるわけでもない。たとえば写真の上にトレーシングペーパーを置き、その上から鉛筆でなぞるというだけの単純作業でも、十人十色のなぞり方をするようなもの。
「コンピューター・グラフィックスなど誰がやっても同じ結果になり、個性を発揮できずつまらない」と以前は考えていたが、今は違う。同じメーカーの鉛筆を使ったからといって、誰でもアングルやピカソのようなデッサンができるわけではない。CGは道具の一つに過ぎない。使い方にもむしろ「個性が出てしまう」。
一方で、コンピューターは鉛筆とか毛筆とかの画材の違いというレベルにとどまらない、別次元の道具でもある。自動車の普及が私たちの生活を変え、日々の考え方にまで大きな影響を与えてきたように、CGを経験することがわたしの思考法だけでなく、感性にも(いいかどうかは別にして)大きな影響をあたえ(てい)るのは間違いない。
その影響で自分がどう変われるのか、楽しみながらCGを描いている。このような絵や動画制作・編集。その前提となるカメラやパソコンそのものの基本知識。どれをとっても難しいし、考えるだけでも億劫だ。何十回も同じ間違いを繰り返すどころか、時にはすっかり忘れてしまう。誰のせいにもできないから、「お前が難しすぎる」とパソコンに当たり散らしながら、とりあえずこの瞬間もパソコンに向かっている。