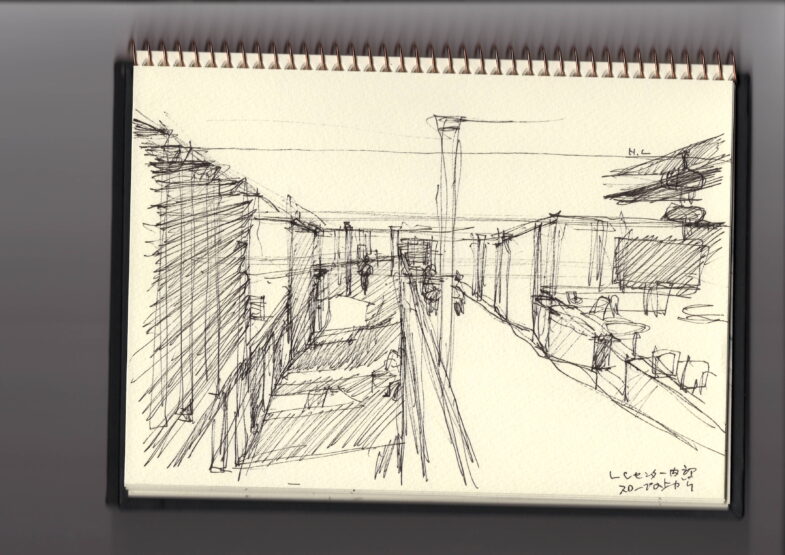あなたは鮫が好きですか?わたしは子どもの頃からずうっと好きなんです。鮫にもいろいろな種類があるけれど、例外なく好きなんです。
子どもの頃、わたしにとって鮫は食べ物でした。今から考えると、わたしの実家では、わたし以外はあまり鮫を好まなかったようですが、わたしはよく食べました。魚好きだったわたしにとって、のどに刺さる小骨のない鮫は、安心して食べることができたからです。蒲鉾にするような大きな鮫ではなく、せいぜい1メートルくらいの、歯のない小さな鮫です。でも、それが鮫が大好きな理由ではありません。
鮫は、かたちも色も生活の仕方も好ましい。あの“JAWS” でその凶暴性が知られるようになったホホジロザメ(ホオジロザメ)ももちろん例外ではありません。好きな理由を考えてみると、①かたちや色の美しさ ②その美しさと優れた身体能力との神秘的なまでの一致感(鮫も実はマグロや鯛などとほとんど変わらない普通の肉食魚です。「凶暴性」なら、鮫以上の魚はいっぱいいます)、あたりでしょうか。
鮫ほど優雅で、身体能力が高く、奥ゆかしく、かつ好奇心にあふれ、お茶目でかわいい顔をした魚は他にいません(恋人の、あばたもほくろもすべて素敵と言っているようなものですが)。そんな鮫を人間に喩えたらどんなひとになるでしょうか。わたしには少なくとも政治家に喩えることはできません。けれど、政治家にこそそういう資質があってほしいと、いつも願っています。