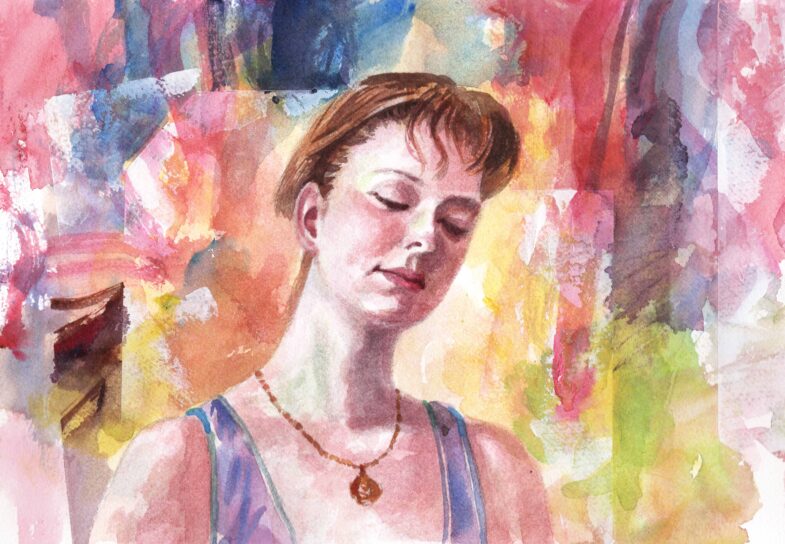12月3日夜11時前、韓国でユン大統領が突然「非常戒厳」いわゆる「戒厳令」を発したというニュースが世界を駆け巡った。その時、真っ先に閃いたのは「北朝鮮が攻めてきた?」「クーデターか?」だった。少しして、軍が国会を封鎖、すべてのメディアは軍に統制される、と追報があったので、これはクーデターに違いないと思ったが、「でも、なんで大統領が?なんで今?」との疑問も湧いた。
翌午前四時過ぎ、戒厳令は撤回された。与党議員も反対に回っているところを見ると、どうも大統領の独り相撲らしい。早速、韓国野党(多数派)が「内乱罪」を適用するよう、法案を提出するとか言っている。国会への弾劾申請は既にされ、ユン大統領も辞任の意向だと報道されている。それしかあるまい。しかし、なぜ今という疑問は残ったまま。
言いにくいことだが、一種の「ボケ」ではあるまいか。ロシアのプーチンがボケまくって、こんなバカげた大戦争を起こしてしまったのに、今も世界の誰一人それを止めることが出来ずにいる。ロシアの現体制が問題だと世界中が知っていたのに、誰も、どうすることできなかった。ユン氏の場合は、幸い正気をとりもどすことができて良かった。
アメリカのバイデン大統領を見て、プーチン同様のことが起きてもおかしくないような気がしていた。まあ、システムが違うからプーチンのような独裁はできないようになっているはずだが、あと数週間で引退するのは、誰にとっても案外ラッキーなことなのかもしれない。しかし、トランプ氏だって急に何をやりだすか、明日のことは判らない。最高権力者がボケたり、なにかに極端に固執すれば最悪の結果を招きかねない、というリスクが世界中のいたるところに口を開けている気がする。