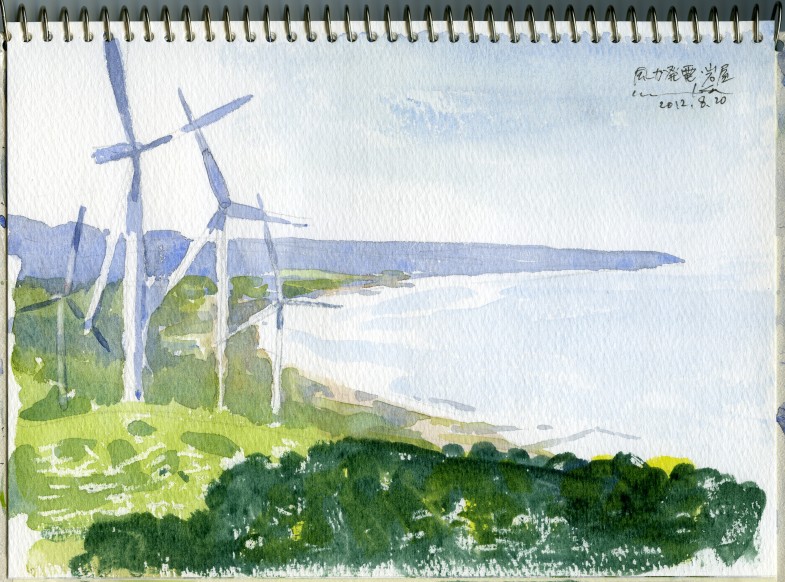世界中で「テレビを見るなど、ぼうっとしている」時間は、集めると一年で一兆時間になるらしい。その時間をネットでつないだら創造的な時間になるのではないか、というような記事を読んだ。確かに、一兆時間という天文学的ともいえる時間が、無駄に流れてしまうならばいかにももったいない。もっともな提案だという気持ちになる。
1609年にケプラーが、太陽系の惑星が太陽を中心とした楕円軌道を描いているとした論文を発表したとき、それは当時の社会にとってどんな意味を持てたのだろうか。400年後の現在から見ればいかにも重要で、その後の天文学に偉大な貢献をしたことは間違いないが、当時の人々がそれを創造的だと評価できたかは疑問だ。仮に、もしもケプラーがその法則を発見する直前で亡くなったとしたら、ケプラーが考え、計算に没頭した時間は無駄な時間と呼ばれてしまうのだろうか。
「テレビを…」についてケプラーまで飛躍しすぎた。一兆時間をネットでつなげば凄いことが出来るかもしれないし、単なる一兆時間の烏合の衆で終わるかも知れない。ただ、みんなが「ぼうっとする」時間を捨てて一斉にネットにつながったら、確実に創造的な何かが抜け落ちてしまうことだけは間違いない。ヌードを描きながら、全く別のことが突然頭に浮かぶことだっていくらでもあるのだから。