「益友」という語を新聞で、初めて知った。益虫、害虫と同じような使い方のようだったから、「害友」もあるかもしれない。
「益友」の語感は最初いい感じがしなかった。付き合う相手を損得で選ぶ感じがしたせいだ。でももう少し読んでいくと、古い友人が「結果として」益友になっている、と受け取れた。おそらく、互いに互いの益友たらんと努力したのだろう。なんとも羨ましい関係だったのだ。
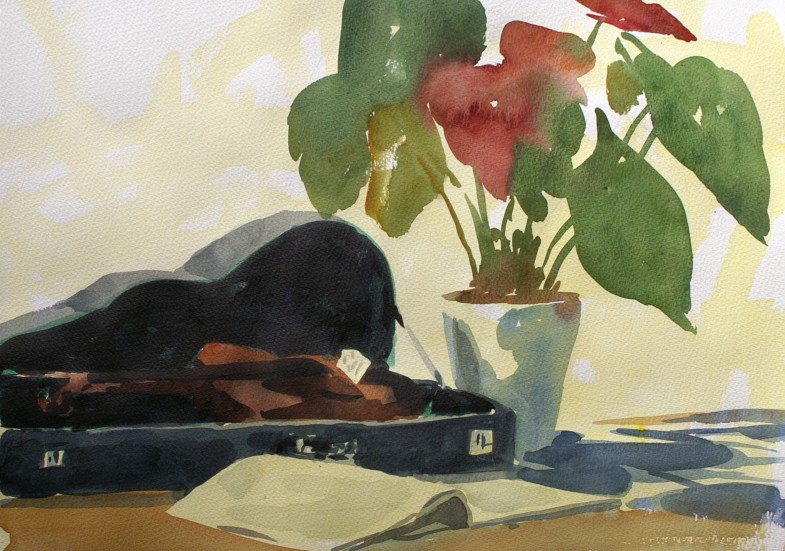
余計な音は聞こえるのに大事な話は聞き取りにくい。それが「難聴」だと医師は言う。肝心の音はちゃんと捉えられない反面、通常なら脳が意識の外へはじき出している音を、制御できずに通過させてしまう状態。
しかし、別に考えてみると、「実際には存在する音」をすなおにそのまま聞いただけのことなのだから、私以外の、または人間以外の生き物はこの「音」を聞いているはずだ。あるいは生き物の種に応じて、音の「聞こえ」にそれぞれの制御があるのではないか。あるいはまた、古代の人とは異なる現代人特有の聞こえかたがあるかも知れない、とも考えた。
病気というのは何なのだろうか?今の人間が、今の時代に合わせたコントロールが出来なくなること?「時代が病気を作る」と聞いたことがある。そういうことかな。