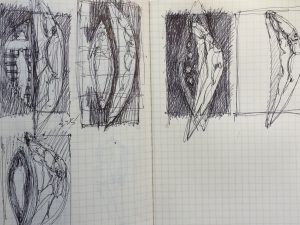L:オレ、少し若返った?緑が増えたような…。
R:特には。
L:そ。希望的観測ってか。
R:ずっと寒いからなあ。枯れないだけマシだよ。
L:数年に一度の寒波だって。最近やたらに何十年に一度とか、聞くようになったな。毎日が一生に一度しかないんだから、そんなことに意味ないと思うけどなあ。
L:50年ぶりの大雪だから備えろって言われても、急に家を耐震化したり、雪かき用に筋肉つけるわけにもいかねえだろう?
R:気象や地震の研究者にとって、だな。あとで調査するまで、今回のことをよく覚えておいてくれってことさ。まあ、大変なことになるかも知れないから、逃げる用意だけはしろって。
L:そうか。でも、実際は逃げることさえできねえんじゃない?
R:そうなんだよ。逃げ道は雪で塞がってますよって言われるだけじゃあ。50年前の経験を活かして、自己判断せよってことだけど、その人たちはもういい歳だろう?今度は雨、それからまた大雪っていう予報だから、今のうちに逃げるのがいいかも。
L:どこへ?50年前に助けてくれた家なんか、もう無いぜ。