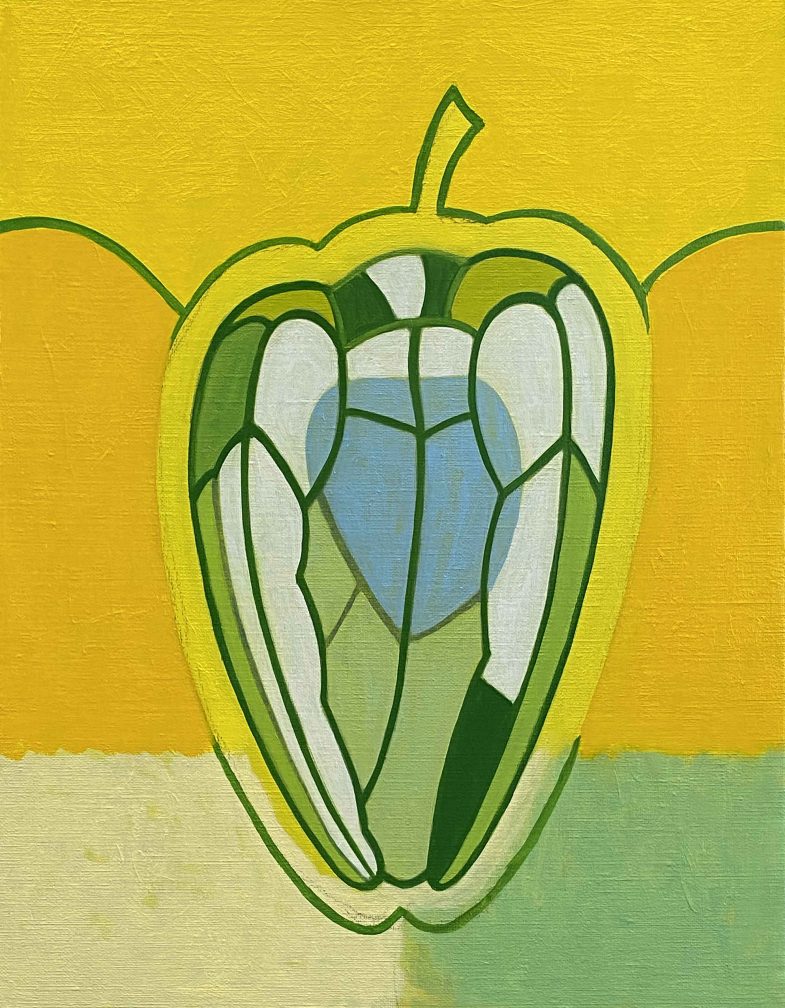
コロナ禍によって初めて体験したものはいくつもあり、どれも貴重なものだが、「オンライン授業体験」もそのひとつ。受ける側ではなく、する側として。
はじめは、「大変だ、どうしよう」という、個人的な、技術的な問題が主だった。デモ制作を考え、撮影し、文字入れ、ナレーションを構成、動画を編集して一本のビデオを作り、学生に配信する。学生からの質問等に応答する。最初の1回分(23分)の授業ビデオを作るのにも、まるまる3週間かかった。そもそも動画編集をしたことがなかったし、パソコンにプリインストールされているソフト以外に選択肢は無かったから、それは必ずしも私の不名誉でもないと思う。その後はだんだん慣れてきて、なんとか8回分くらいまでは準備できた。
ところが、非常事態宣言が、首都圏でも5/25を境にどうやら解除されそうな雲行きだ。解除されると、オンライン授業から従来の「対面授業」に戻る、だろう。でも、せっかくビデオの準備したのに〜、などとは思わない。やっぱり学生の顔を見ながらやった方が楽しいし、ビデオの準備をする過程でも、得たものは少なくなかったから。
解除について心配なことがある。せっかくオンラインでの(一部)授業が、可能なだけでなく寧ろ有効だということが、サッと忘れ去られるのではないかということ。オンラインでの(一部)会社経営が成り立つこと、出勤しない方が効率よく仕事できること等に、会社員自身が気づいたこと。それが「解除」によって以前の状態に戻る。そちらの方がむしろ問題ではないか?なんとなく、すべての文化的尺度で世界上位にいると錯覚していた日本人が、実はオンラインという視点では「先進国中ではずっと下だ」、という事実を「見なかったことに」してしまうこと。それらが心配だ。(感染症対策、重傷者の医療体制はまた別の次元の問題として)「オンライン」に関しては、もうオールド・エコノミストたちと同じ地面にいつまでも立つ意味はないのではないか、と考えさせてくれた私の「オンライン体験」です。