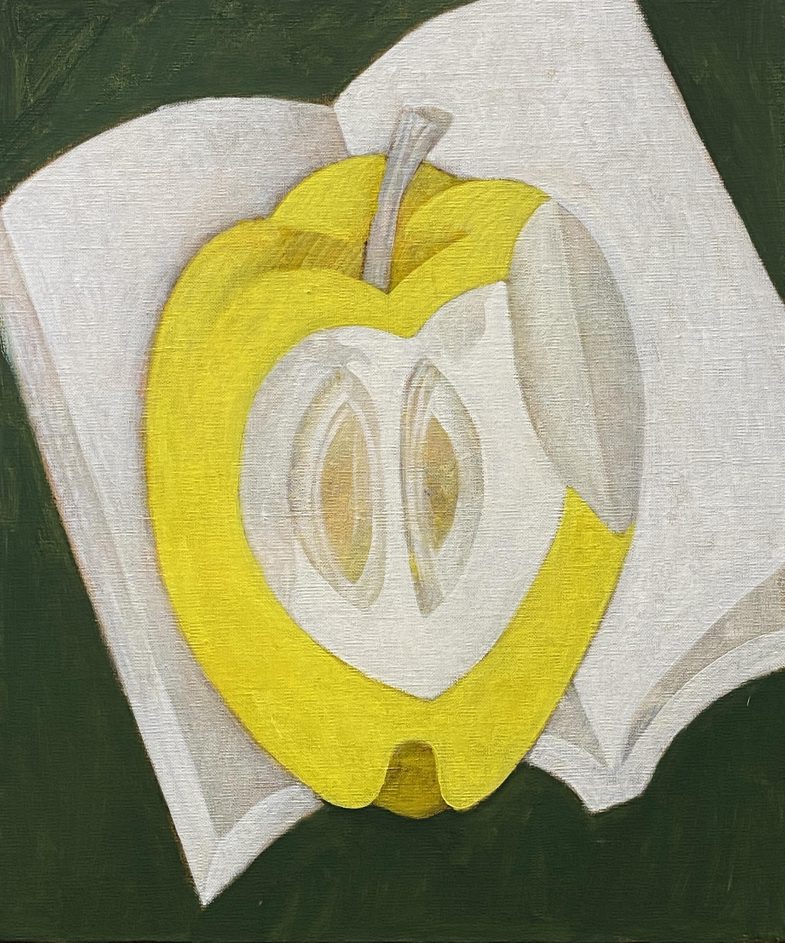
特にダイエットをしていなくても、体重やカロリーに気をつかっている人も数えれば、大多数の人がダイエットに関心くらいはを持っているはずだ。ダイエットといえばすぐ体重を減らすことだけにとらわれがちだが、短期間で1~2㎏体重を減らすだけなら、(健康であれば)誰でもできると思う。難しいのは、数年単位の長期にわたって、適切なダイエット(体重だけではない、総合的な体調管理)をキープすることだろう。
わたしはダイエットを始めてまだ8ヶ月しか経っていないので、その難しさをまだまだ分かってはいないと思うが、たったそれだけでの期間でも、結構たくさんのことを経験した。その第一は、これまでの自分があまりにも自分自身の身体について無知・無関心だったということ。
カロリーや栄養についてだけでなく、食物について、食事・調理について、消化・吸収などの生理、運動と生理、食べたいという欲求やその心理などについて、潔いほど完全な無知。食品の値段だって時にはダイエットに直結するのに、まったく無関心だった。
プチ断食でも1、2㎏くらいはすぐ体重を減らせる。けれど半年、1年と、健康をキープしながらダイエットを続けるのは、最低限の知識と自分の身体に対する観察力がないと無理だと解ってきた。それと自分の生き方とがどう結びつくのかについても、なんとなく意味を感じ始めた。
考えてみると、これまで自分の身体についてこんなにも無知でいられたのは、まずは健康だからである。ならば、これまでの日常を今後も続けていけばいいわけで、検診でメタボ予備軍と言われたからといって、ある意味で「非人間的」ともいえるダイエットなどする必要がないのではないか。いま健康な人が「もっと」健康になることに、その人自身にとってどんな意味があるのか、という疑問・反論があっても当然である。
けれど、もう一歩考えてみると、何がどう作用して現在の健康を保てているのかということは、「いま健康だ」という状態だけを見ても分からない。人は気まぐれ。食べ過ぎ、飲み過ぎは日常茶飯事。年齢による変化も当然ある。それらを通してもなお健康でいられるには今のままでいいのか悪いのか。そこにちゃんとした知識がないと、いつか自ら健康を害することさえやりかねない。ウオーキングや筋トレのやりすぎもよく聞く話である。
ダイエットは自分を知るための方法のひとつだ、とわたしもやっと気がつき始めたのである。

