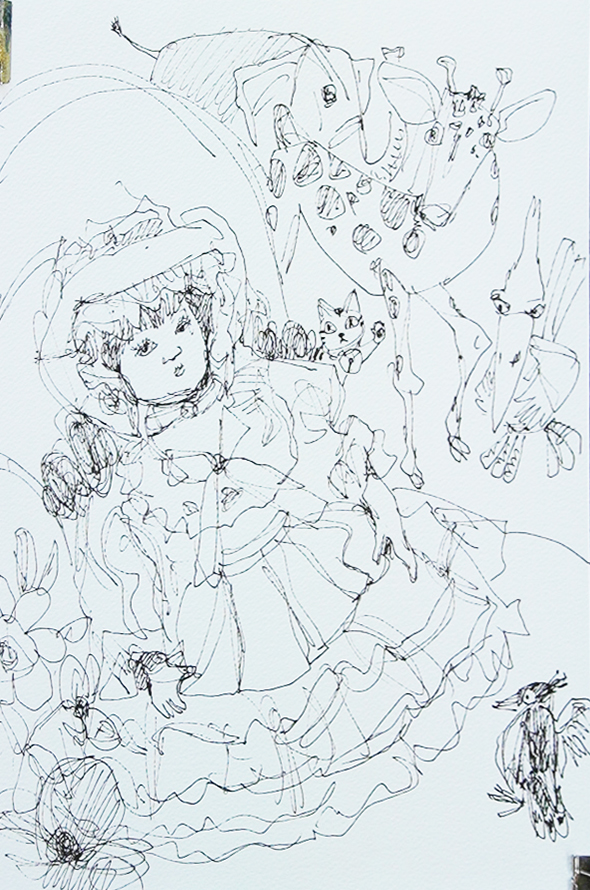水曜日の水彩教室で、課題として描いてみた。相当急いで描いても、時間内に描くのは難しい。急いでいるせいで、もやい綱なども描き忘れ。当たり前だが、やっぱり急いで描くのは楽しくない。失敗しても、ゆるゆる描くのがいいな。
それでも、青い絵の具を使うだけで爽やかな気分になれるのは絵を描く人の特権か。
技術的な課題がひとつ。この絵ではマスク液を使ってみたが、専用のノズルで細く描くはずががドバっと出てしまったり、逆に詰まったりなど、白抜きに難儀した。マスク液を薄めて筆で置く方法もあるし、あとから修正液やガッシュなどの不透明絵の具で描くなどいろいろあるが、教室でいろいろ試している時間はない。とりあえずはもう少し上手にマスク液を扱う方法を見つけ出さないといけない。
明日(いや、もう今日だ)で9月も終わる。「光陰矢のごとし」の「矢」なんて今や「スロー」の代名詞(それでも新幹線並みの時速200kmチョイ)。一日が矢の10倍以上早く過ぎる感じだなあと思って計算してみると、実際、赤道上での地球の自転速度は時速約1700kmで、矢の早さの8倍くらいの速さで地球が回っているのだった。体感に近かったのにむしろ驚いた。