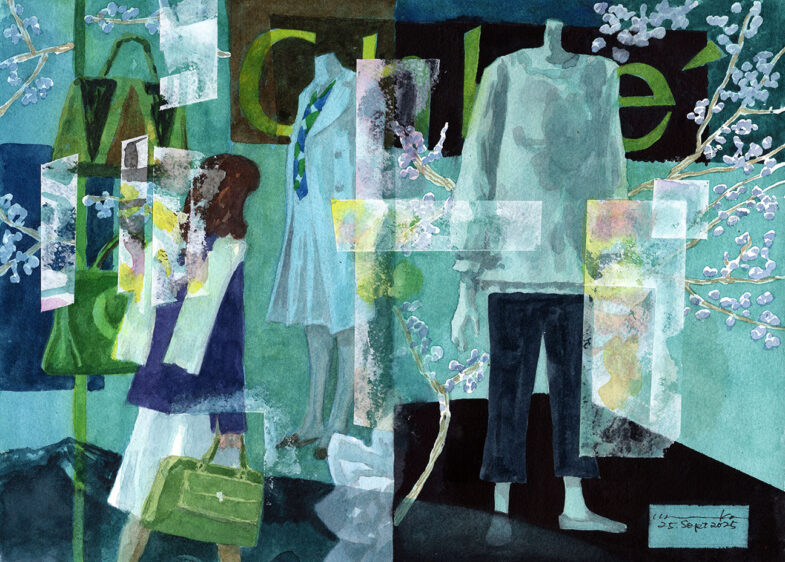現代(のたくさんのアイテムやシステム)についていけない、という人が大勢います(いるはずです)。高齢者の方の割合が多いだろうということは容易に想像できますが、若い人の中にも、同じように感じる人だっているはずです。
ついていけない、と感じる対象の多くは、いわゆるIT関連のこと、パソコンやスマートフォンの使いかた、またそれを使ってのオンラインでの公的、準公的な登録や予約などのようです。例えば納税申告。今でも紙での申告は可能ですが、オンラインで申告する人の割合が増えるにつれ、紙での申告、ちょっと混み入った事情があったり、不明な点があって税務署に訪ねたい場合など、窓口が縮小されていたり、そのための予約を別にとらなくてはならず、何度も足を運ばなくてはならなくなった、などとよく聞きます。
オンラインで出来たらどんなに楽かと、パソコン、スマートフォンでサクサクできる人を羨ましく思っています。「覚えればいいじゃないか」。それはそうなんですが、関節も硬く指も動きにくいうえ、目も見えにくくなるので拡大すると情報が画面に入りきらず、スクロールするとその画面がどこかに行ってしまう、なんてことの繰り返し。しかも、何度くり返しても覚えにくい。そういう事情は若い人には想像しにくいでしょう。
政治家のように有能な秘書を雇えるなら問題ないかもしれませんが、そもそも高齢者には収入の道が閉ざされているんですよね。いまは自助努力で、なんて言われる時代だから人に聞くことさえ憚られるようになってきました。結局できるようになれず、仕方ないと諦めていくわけですね。
でも、日本全体がそれでいいんですかね。本人が諦めてくれれば行政としては何もしなくて済むし、若い人にとっても負担が減って助かる、そういう感覚でいいんでしょうか。一種の切り捨て、かつての姥捨て山が人目に触れないところで全国に出現し、一定の年齢以下の人だけが生活を満喫するのを、豊かな社会と呼ぶんでしょうかね。まあ、それは極端な例だとしても、誰が総理大臣になるのかの前に、どういう社会を作るためにどういう人が必要かを考えるのが先ではないでしょうか。