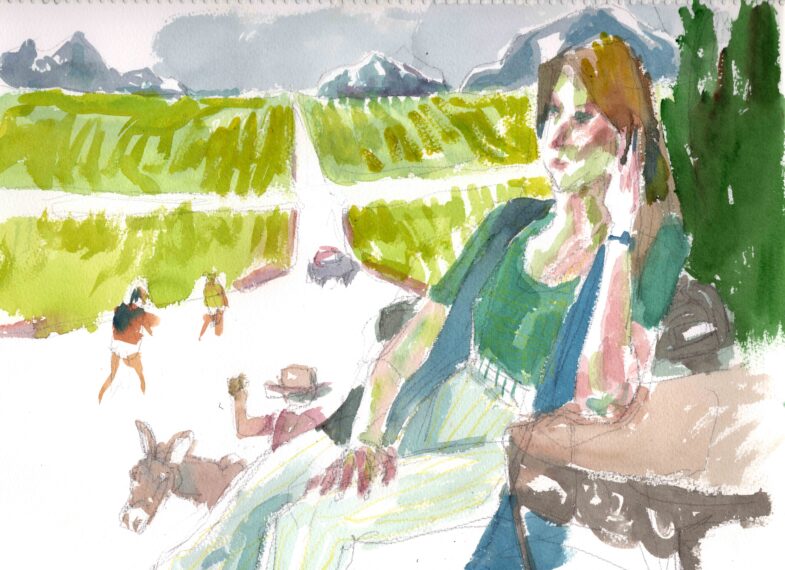
中央アジアのジョージアで先日、国会議員の選挙があった。たまたま日本も一昨日、衆議院(議員)選挙があり、自公が大幅に後退したばかりなので、ついでにでもちょっと目を向けて見たらどうかな、と記事にしました。日本の選挙結果は、概ね予想通りの結果になったようですが、わたしは、ジョージアの選挙結果も、衆議院(議員)選挙と同じくらいの関心を持って見ていました。
「なんでジョージアやねん?」。そもそもジョージアという国が地球上のどこにあるか、日本人の中には知らない人もいるかもしれません。ぜひ、スマホで地図を見て頂きたいと思います。ワイン好きの人などは知っているかもしれませんが、ニュースにも滅多に出てこないし、出てもほぼロシア関連ですから、そちらの方に注意力が向くのも、ある意味仕方ありません。
ジョージア、ウクライナそしてモルドバ。いまウクライナ戦争が黒海周辺を発端に行われていますが、この3国は黒海に面して繋がっています。そのジョージアの国政選挙(定数150)で、親ロシア派の議員が多くを占めました。大統領(ちなみに、女性です)自身がこの結果を認めず、(与党ではなく!)野党と一体になって「国民的なデモ」を呼びかける事態になっています。ロシアが絡むと、必ずと言っていいほど起きる「違法投票」「選挙結果の改ざん」ということです。どういうことなんでしょうか?
少しだけ歴史を調べ、少しだけ想像力を働かせば、容易に答えにたどり着く事ができるでしょう。でも、今はそれを書く気持ちが起きません。

