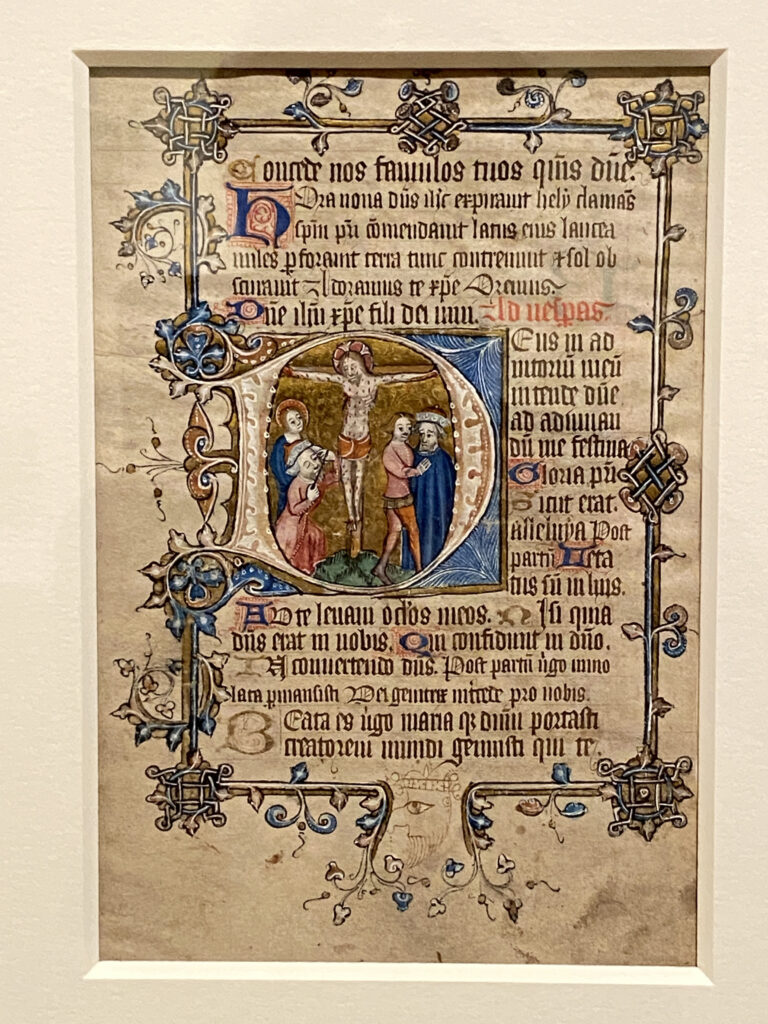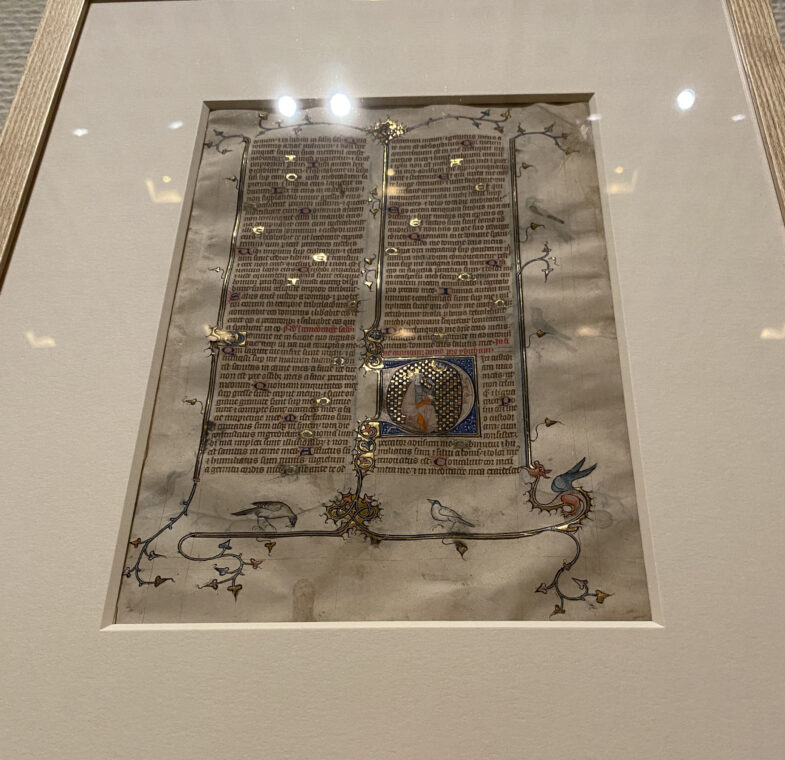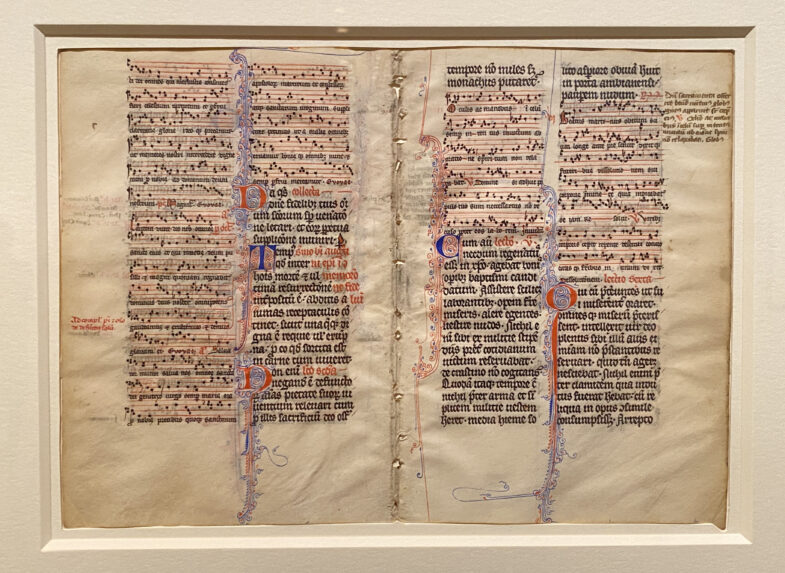今日は都知事選の投票日。期日前投票では前回を上回っているらしい。ということは当日の投票率が下がるということでもあるし、第一この暑さでは出かけることができない人も少なからずいるに違いない。なぜ電子投票ができないのか、そこにも今の日本の問題が顔を出している。
先週金曜日、銀座から青山へと画廊を回ってきた。銀座で都知事選の応援演説をしているところにぶつかり、ちょっとだけ立ち見した。関係者が、「通行の邪魔にならないように」と声を張り上げていたが、あえて通行人の多いところを選んで演説しているのだから、邪魔にならないわけがない。
選挙制度そのものをおちょくって見せる政党もあれば、ほぼ習慣のように立候補する個人もあったりするが、今回は現職+政権与党VS野党候補、それに話題の新人が絡むという、典型的な従来通りの舞台となっている。そこにこっそり食い込もうとする寄生虫集団が見え隠れ(今や堂々と、だが)する構図も変わらない。変わらないのか変えたくないのか判らないが、有権者としては何も考えたくないというのが本音なんでしょう。いや、もしかするとそれがメディアの姿勢によるものかもしれないけれど。
諦めでもなく、投げやりでもなく、無視するでもないが何も行動したくない、投票にも。そんな感じに見える。で、結局は何も変わらず。それが「安心・安全」と感じる人もいる。とはいえ、世界は一瞬の停止もないのだから、積極的な意思として「変えない」というのでもない限り、一周遅れ、二周遅れとなっていくのは当然だ。思考停止の結果である。
もちろん、ただ流れに乗っていければそれでいいとも思わないが、思考停止を一種の脳死のようなものだとすれば、自分の身体が誰かに何かされてもどうすることもできない。それでいいんですか?と訊いても、考えたくないというのだろうけど。