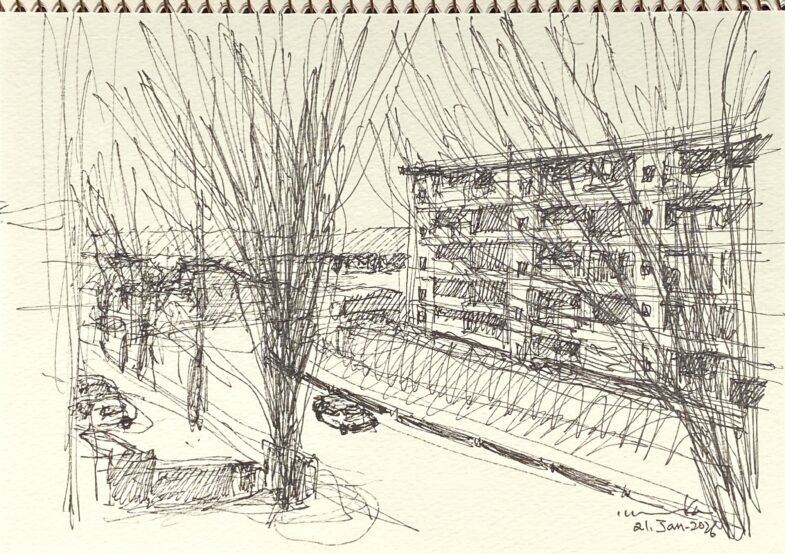皆さんご存知のように、トランプが米軍を使ってマドゥーロ大統領夫妻を拉致拘留し、すでにアメリカへ移送されたらしい。手錠、目隠しされたマドゥーロ大統領の写真も既にSNS上に公開されている。当日、トランプはこの “テロ行為” を、こともあろうにプーチンと同じ「特別軍事作戦」と呼び、“非常に上手くいった”と、自画自賛のメッセージをSNSで発信した。しかも、「今後起こることはアメリカが管理する」と付け加え、ベネズエラの副大統領に、「このあとどうすべきかわかってんだろうな?下手なことしやがると、もっと痛い目に合うぜ」と圧力をかけた(BBC報道から一部要約)。
よくもまあ、ここまでプーチンのサル真似をするほど彼の崇拝者なのかと呆れるけれど、国際的な反応は「様子見」。マクロン(仏)は一応抗議したけれど、英国のスターマー首相が「肯定的」なのがオカシイ。アルゼンチンとのフォークランド紛争のことを、誰かが “特殊な言い回し” で彼に吹き込んだか?
麻薬云々と、そりゃあ、しばらく前からトランプがグズっていたけれど、国際的には何の証拠も示さずに、「こいつらは麻薬シンジケートの仲間だ」と一方的に断定するだけで、米軍がボートの乗員を射殺し続けた。さすがに共和党の中からでさえ、「それはちょっとマズいんじゃない?」と懸念が出るほどだった。
極端にうがった見方をすれば、トランプは「アメリカという国を売ってまで」、“プーチンを助けた” 、と見ることも可能だ。つまり「アメリカだって、プーチンと同じことやってんじゃん」ということで、今後「ロシアへの圧力をゼロにする」ことが、「論理的に可能になった」。もしそうならば、(大多数の、と思いたいが)アメリカ国民にとって、それこそ、いわゆる「売国行為(こんな言葉を使うこと自体が嫌だが)」だと思うけれど、プーチンから見ればまさに「忠義」そのもの。
事実、「これでもうアメリカはロシアを批判できなくなった」という論調が国際的に支配的になってきた。
トランプが、アメリカ合衆国を「法を無視するギャング国家」、「石油利権を狙った強盗国家」に貶めていると感じるけれど、アメリカ国民の多くはそうでもないようだ。「麻薬は悪」「それを正すトランプは正義」。まるで、フィリピンのドゥテルテ元大統領の「拡大コピー」?国内の物価高への批判を外へそらすタイミングだとしても、将来的に禍根を残すはずだ。