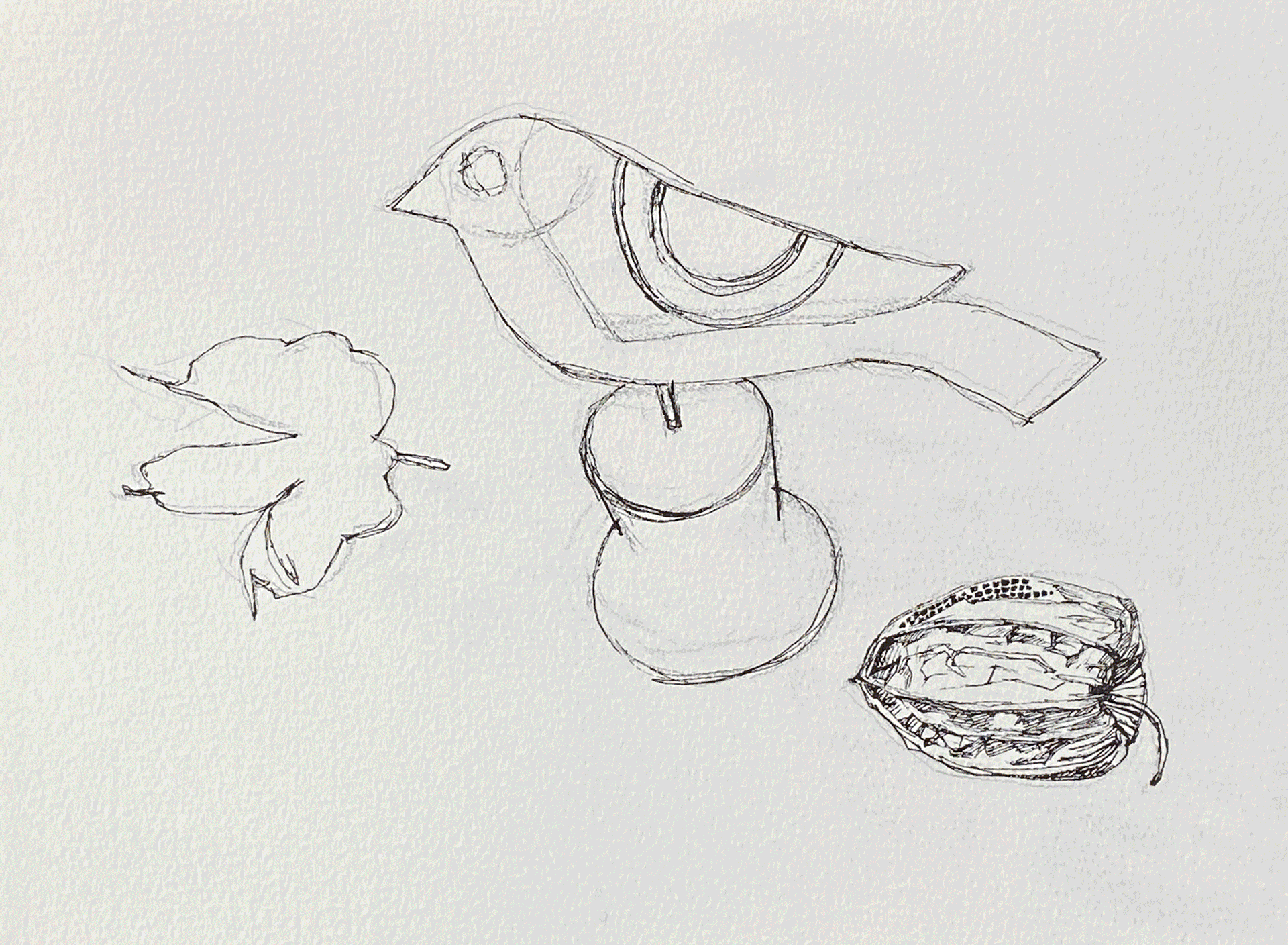
Quan vaig dibuixar el dibuix el vaig publicar l'altre dia al meu blog、Vaig fer algunes fotos pel camí.、Vaig provar de connectar-lo。Durant els últims sis mesos, la meva ment ha estat ocupada amb el "vídeo" i la seva edició.、De totes maneres, feu tantes fotos com sigui possible pel camí.。
Mentre caminava、La paraula "no et perdis" prové dels auriculars.、atrapat a la meva orella。Un cert home de negocis diu: ``Jo ○○ per estar al dia de les tendències de l'època''.、Crec que era una cosa que normalment s'ignoria.、“Les onades dels temps、Si estiguessis enmig d'aquestes onades, ho entendries?"、El meu esperit rebel habitual、En particular, sembla que ha "salvat" aquestes paraules.。
Potser、Coses que em preocupen actualment quan edito vídeos、És per muntar les "ones dels temps"? En la meva pròpia història de la pintura, l'''era de la pintura'' ja ha acabat.。Recordo que ho vaig escriure en algun article.。Tot i això, encara estic dibuixant.、Ja s'ha acabat l'època de la pintura? ho és、Perquè sento que "la pintura és el meu destí".。Per molt antiquat que sigui、No es pot evitar si és el destí、Perquè això és el que penso。- Aleshores、Per què vídeos ara?。
D'una banda, els ordinadors s'han tornat més fàcils.、Això és perquè les "imatges en moviment = imatges en moviment" estan al vostre abast (?)。El món està ple de vídeos。El món del vídeo al qual només hi podien accedir empreses especialitzades com les televisions.、els joves utilitzen telèfons intel·ligents、Instagram、YouTube, etc.、Ho escric casualment, com si escrivia un diari.。油絵具じゃなくたって、水彩絵の具じゃなくたって、自分たちの新しい絵の具で絵を描くよ。そういわれているような気がする。それなら私も新しい道具で絵を描いてみたい。però、そう思うこと自体時代の波に乗り遅れまいという心理なのか、いまは判断できない。(現状ではまだ全然ダメだが)、もう少し頑張れば私も「新しい絵の具」で、また新しい自分の絵を描けるのではないか、となんとか希望をつないでいる。

