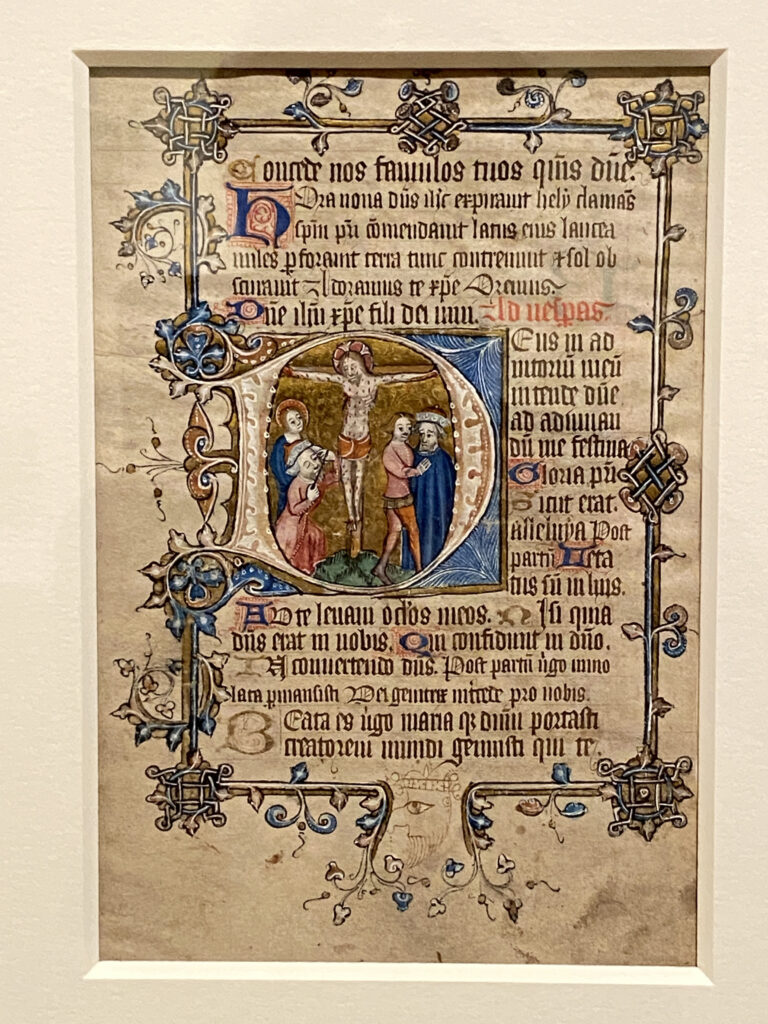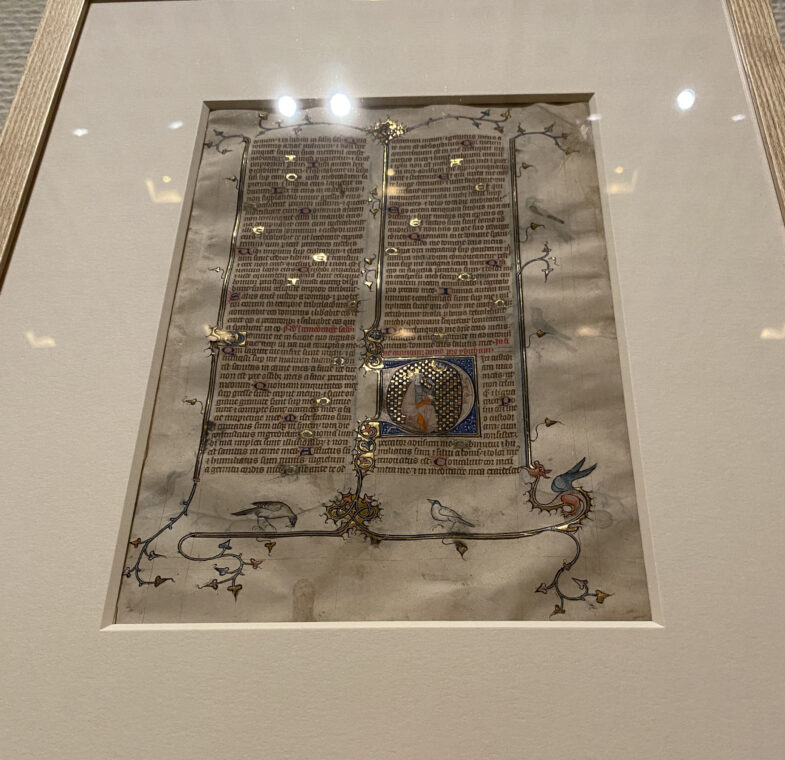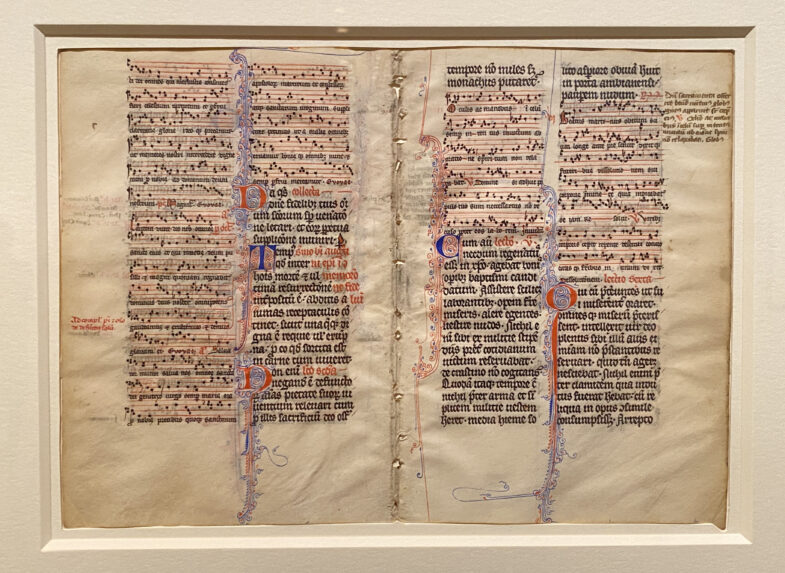Leo ni siku ya uchaguzi wa gubernatorial wa Tokyo。Inavyoonekana, kupiga kura mapema kulizidi ile ya zamani.。Hii inamaanisha kuwa zamu ya wapiga kura itapungua kwa siku.、Kwanza kabisa, lazima kuwe na watu wachache ambao hawawezi kwenda kwenye joto hili.。Kwa nini huwezi kupiga kura za elektroniki?、Maswala ya sasa ya Japan pia yameangaziwa.。
Ijumaa iliyopita、Nilizunguka nyumba ya sanaa kutoka Ginza kwenda Aoyama.。Aliingia kwenye hotuba huko Ginza, ambapo alikuwa akitoa hotuba ya kuunga mkono kwa uchaguzi wa gubernatorial wa Tokyo.、Nilisimama hapo kwa muda。Watu waliohusika、"Usiingie katika njia ya trafiki," alilia.、Wanachagua mahali kwa makusudi na wapita njia wengi kutoa hotuba、Hakuna njia ambayo haitaingia njiani。
Ikiwa kuna vyama vya siasa ambavyo vitafurahisha mfumo wa uchaguzi yenyewe、Watu wengine hukimbilia ofisi karibu kama tabia.、Wakati huu, msimamo wa sasa + chama tawala dhidi ya mgombea wa upinzani、Ni mpya ya mada mpya inayohusika.、Ni mpangilio wa kawaida wa jadi。Kundi la vimelea kujaribu kwa siri kuingia ndani linaonekana (sasa kwa kiburi、Lakini) muundo unabaki sawa。Sijui ikiwa haibadilika au ikiwa sitaki kubadilika、Kama mpiga kura, ukweli ni kwamba hataki kufikiria juu ya kitu chochote.。hapana、Labda hiyo ni kwa sababu ya mtazamo wa media.。
Sio kukata tamaa、Sio vilema tu、Sijali, lakini sitaki kutenda、Pia juu ya kupiga kura。Inaonekana kama hiyo。katika、Mwishowe hakuna kilichobadilika。Watu wengine hugundua kuwa "ni salama na salama."。Hiyo inasemwa、Ulimwengu hauna kituo cha muda、Isipokuwa una nia nzuri, haubadilishi、Mduara umecheleweshwa、Kwa kweli, ni mikono miwili nyuma。Ni matokeo ya kusimamishwa kwa mawazo。
Kwa kweli、Sidhani hiyo ni sawa kwa muda mrefu kama ninafuata mtiririko、Ikiwa mawazo ya kuacha ni kama aina ya kifo cha ubongo、Hata kama mtu hufanya kitu juu ya mwili wako, huwezi kufanya chochote。Je! Hiyo ni sawa? Hata nikiuliza、Nadhani hawataki kufikiria juu yake。