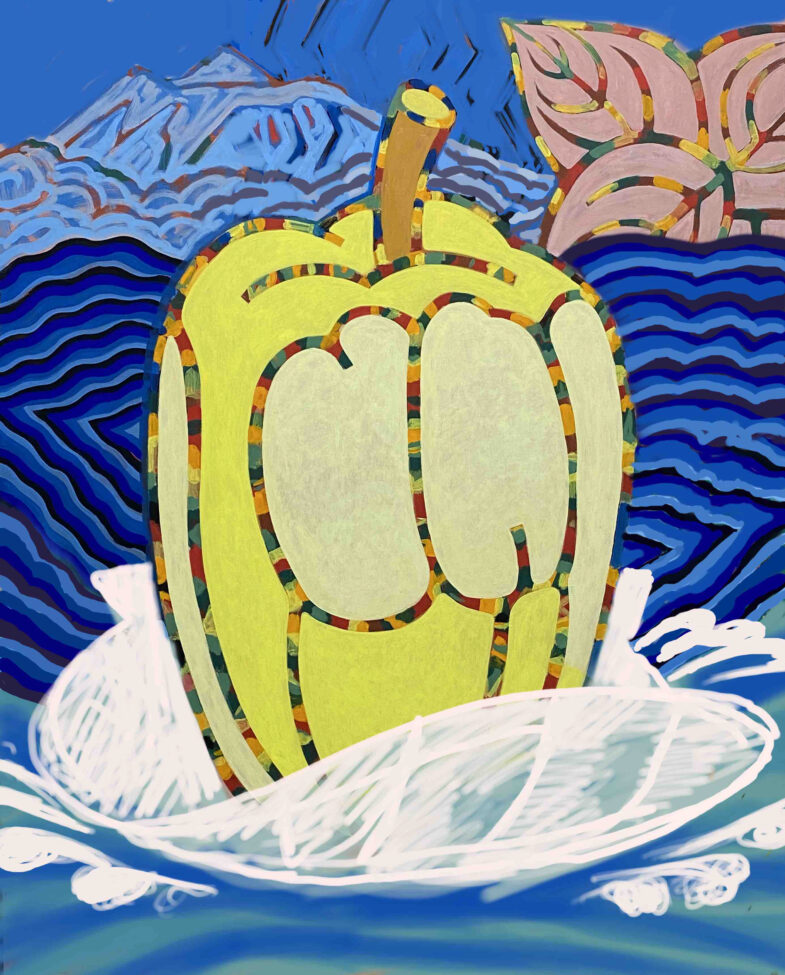Sio tu wewe bet pesa、「人生を賭ける」「命を賭ける」という極端な経験をする人はどのくらいいるだろうか。1%か、もっと少なく0.001%くらいかと思ったが、よくよく考えてみるとほぼ100%の人が、実は経験するのではなかろうか、と思い至った。
たとえば結婚。ある程度納得のいく情報交換、Hata ikiwa unapitia mchakato na kuishia kuoa、"Wengine ni wengine"。Kutoka kwa kile nilichojifunza juu ya mtu huyo mwingine、Lazima kuwe na mambo zaidi ambayo sijui、Mahali pengine ninaamua, "Noo"。na、Kimsingi, tunatumia maisha yetu yote pamoja、まさに「人生を賭ける」といっても決して過言ではない。特に地方にあって、長男である夫の家に嫁ぐ(“とつぐ”という言葉自体がその内容を示しているが)女性においては「清水の舞台から飛び降りる」以上の決断だと思う。わたしのようなヘナヘナ人間には、その決断力だけでも驚嘆に値する。
朝起きて、ご飯を作り、食べ、会社や学校へ行く。帰宅帰りにスーパーで買い物をして晩ごはんを作り、食べ、洗い物をする。明日のためには、もう風呂に入って寝るしかない。そんな“日常”さえ突然断ち切られたりすることがあるのは、ニュースなど聞かずともそこら中に満ちあふれている。「それは特別な場合でしょう?」と思う人が多いのは、それだけ「人間」に「文化」がある証拠なので嬉しいことではあるが、(人間以外の)動物ではそうはいかない。子育て中の母親が、エサを探しに行く途中で他の動物のエサにされてしまうことは「自然の一部」。それが「日常」なのだから、少なくとも(人間以外の)動物においては「毎日が命がけ」は現実そのものに違いない。
Lakini、動物にとっての「命がけ」は「賭け」ではない。いかに命がけであろうと、それは「日常」である。「賭け」には、それを「賭ける」意識が必要だ。失敗したら何かを失うが、その何かと賭けるものとの「差額」のような意識がなければ、それは賭けではない。つまり「リスクの意識」の有無である。リスクと利益の計算を、一定の根拠に基づいて行動に移すこと。それが「賭け」だとしたら、人間なら、生まれてこのかた、ずっと賭け人生だと言ってよいのではないか。違いがあるのは根拠の確かさと失敗したときの覚悟だけ。もしかしたら、その覚悟の有無だけを人は賭けと呼んでいるのかもしれないが。