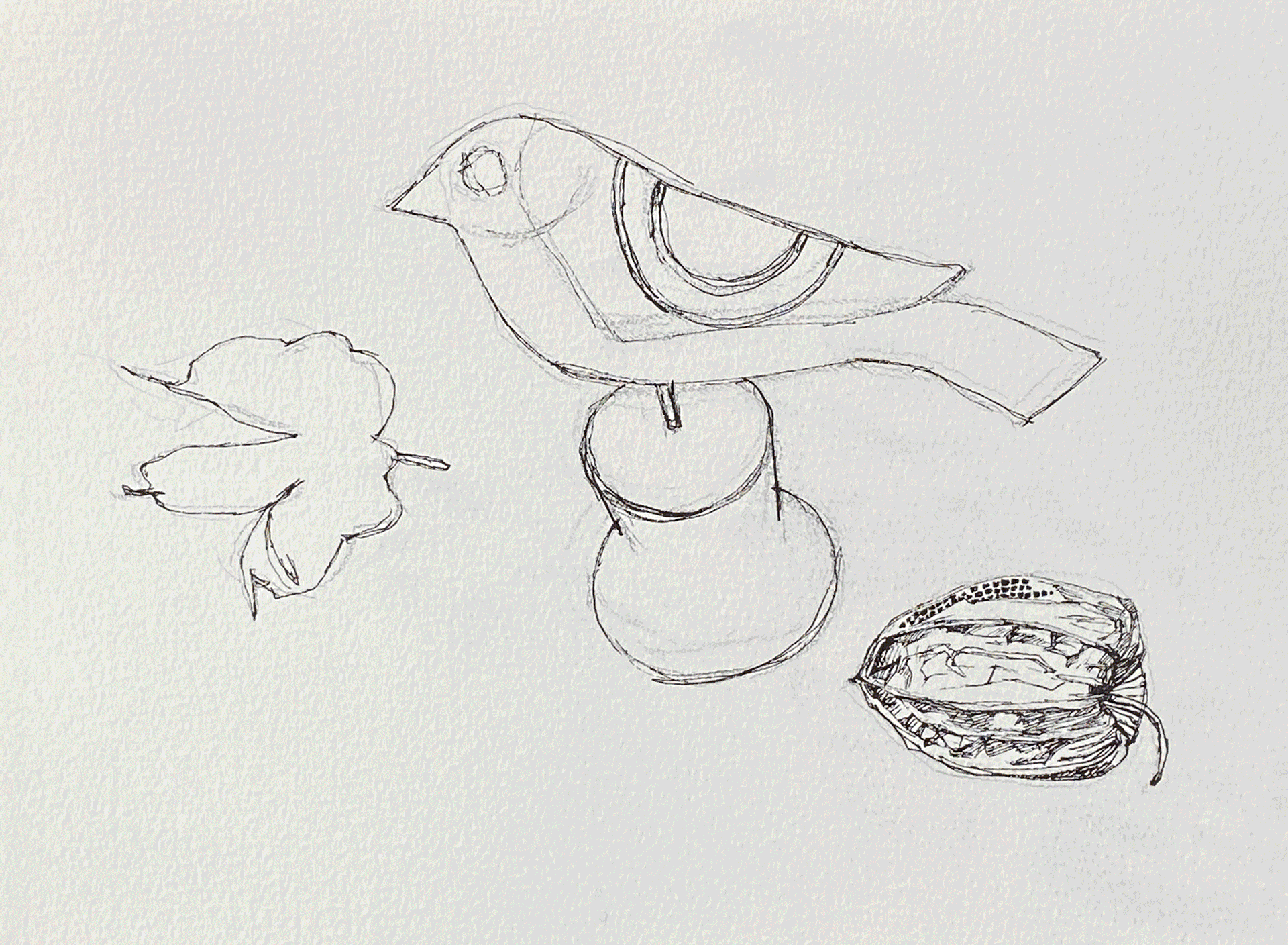メタボ予備軍との判定をきっかけに、渡りに舟とウオーキングを始めたことは何度も書いた。早朝ウォーキングが以外に気持ちよく、それが続けられた理由であることも書いた(急激に始めたせいで少し膝を痛め、自重中)。プラス面だけでなくこんなマイナス面もあるが、足腰がしっかりしてきた実感もある。
けれど「メタボ予備軍からの脱却」という目標から考えれば、まずは「体重を減らす」ことが最優先課題だ。運動は健康には有効であるものの、体重減少という点ではあまり有効ではない。本命は「カロリー制限」である。
前提条件として、自分の「適正体重」というものをまずは知ることから。多くの人にとってはすでに常識なのだろうが、自分としてはまともに向き合ってこなかったから、基礎知識が全然足りないことを感じた。就我而言、適正体重は現状から-10kg。但、それはすでに「絶望的」。
私は「適正体重」の方を諦めることにし、とりあえず2ヶ月で―2kg。これならたやすく達成できそうだ(と最初は思った)。目標体重と仕事の内容(肉体的か事務的かなど)から、必要カロリーを計算する。就我而言、体重1kgあたり25~30kcalとして、それからここ数日に実際に摂ったカロリーを計算してみると、「恐ろしい」現実が・・・。気を取り直して、目標カロリーを「3食+おやつ」に振り分け、実際のメニューとカロリー表とを試算してみると、にわかにメニュー」が「仮想現実」感を帯びてくる。「小太り」のままでもいい理由を探しはじめる…。