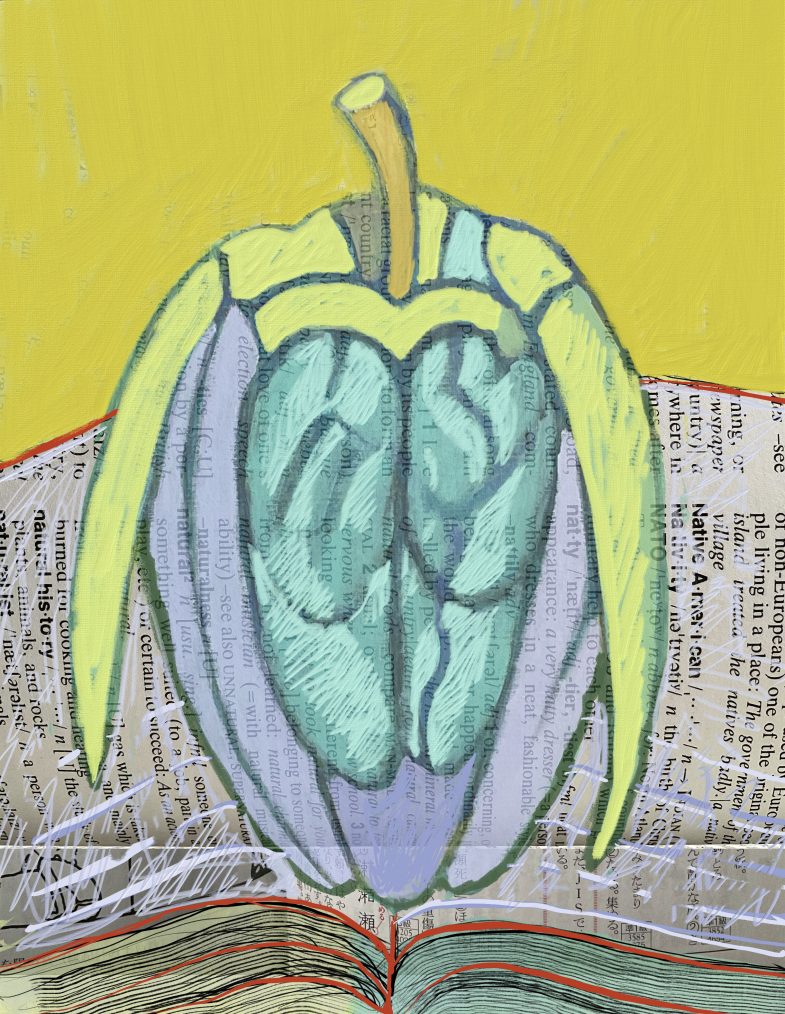先日までと違うソフトで描いてみた。イラスト系のソフトにはたいてい「チュートリアル」という手引きのvideoがついていて、それを見てからやるのだが、手引き通りにスムーズにいったことはただの1回もない。最初の最初からつっかえて、そんなはずは、と何度もビデオを見直して、それでもなぜか手引きのようにはいかないのが「普通」。のたうち回ったあげく、ようやく分かった気になっても、最初の最初にたどり着くまでにそこからさらに数時間もかかったりする。手引きではたったの1秒で通過しているのに。以前のわたしなら怒り狂ってパソコンを破壊しかねなかった。今もかなりイラつきながら、そういうイデオムなのだと思うようになってきた。
ソフト開発者の多くは画家やイラストレーターではない(らしい)。チュートリアルで「やり方を実演する」デザイナーも、(説明時間がかぎられているから)それぞれ自分のレベルで早口で説明するのだから、初心者は戸惑って当然。そのことがが分かっただけで、だいぶパソコンの傷が減り、わたしの血圧も安定してきた。
新しいことを覚えるには膨大な時間と労力が必要だ。パソコンの知識・理解力から考えると、わたしには普通の人の3倍以上の根気が要るようだ。コロナ禍の今、たまたまその時間が与えられたのだと思っている。
多くの人がそうであるように、コロナによって私の生活も大きな影響を受けている。つらい影響の一方で、わたしは数年前と人が変わったように歩くようになり、歩きながらラジオでいろんな知識を得るようにもなった。偶然にパソコンも入れ替え、様々なソフトも導入した。
考えてみれば、コロナ禍があろうとなかろうと、わたしはもっと早くに自分を変える必要があった、と思う。もしコロナが無かったら、わたしは自分を変える最後のチャンスを失っていたかもしれない(実際にはもう手遅れだとしても)。人類史的にみれば、ウィルスは多くの生命の進化に寄与しているという面もあるらしい。―かすかにうなづく自分がいる。