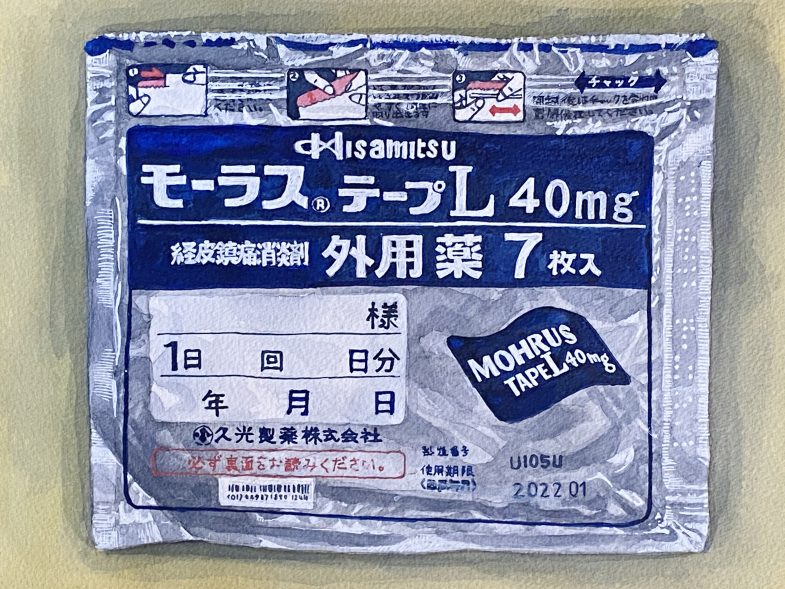Bago magising、Pinangarap ko ang isang poster na Kokoshka。2019Ang "Vienna Modernism" na eksibisyon noong Mayo 2019、Ito ang pangarap ng pagpipinta nang makita ko ito sa Uematsu-kun mula sa Osaka.。Ganap kong nakalimutan ang tungkol dito、Nang walang babala、Bigla itong lumitaw sa panaginip ko。Bago mawala ang aking memorya、Sa ngayon, sinubukan kong "halos magdagdag" sa canvas ng ika -100 na isyu na iginuhit ko (siyempre, ang mga poster ng Kokoshka ay mas sopistikado).。
Sa nakaraang linggo o higit pa、Ako ay nasa isang estado ng pagkantot kapag ginagawa ko ito ... ang direksyon ay naayos - ang paraan ng pagguhit ay halos maayos - "Ngunit hindi ako makakakuha ng anumang mga kongkretong imahe" - Nakaramdam ako ng inis、Gumuhit ng isa pang maliit na larawan、Patuloy kong iniisip ito sa lahat ng oras habang gumagawa ng maliit na trabaho at paglilinis ng atelier。Ngunit ... walang dumating、Nagsisimula na akong makaramdam ng kaunting pagkabalisa。
Ang Oscar Kokoschka ay ang ika -20 siglo、Marahil siya ay itinuturing na isang "expressionist painter."。Ipinanganak sa Austria (Pangwakas na nasyonalidad ay nasa UK)。Namatay sa Switzerland。Sumali rin siya sa mga separatista ng Vienna kasama sina Klimt at Schiele.、Gumagawa siya ng isang kamangha -manghang pagtatanghal (natutunan ko ito sa kauna -unahang pagkakataon mula sa kronolohiya).、Tila nagturo din siya sa Bauhaus.。Ngunit sa huli hindi ako sumali sa pangkat.、Siya ay isang tao na naglalakad sa mundo mag -isa。
Upang maging matapat、Ang kanyang mga kuwadro ay hindi pa rin naiintindihan、Hindi naman ako ganito。Ngunit kahit papaano, isang bagay tulad ng "timbang" ng trabaho、Hindi niya ako pinakawalan。- Pagkalipas ng tatlong taon, kaninang umaga, bigla itong nagsimulang tumayo bilang isang unan sa panaginip.。- Huwag kalimutan ang paghahayag ng iyong mga pangarap、Agad akong tumalon sa itaas at hinanap ang katalogo ng eksibisyon.。
Sa isang panaginip、Pakiramdam ko ay sumigaw ako "Ito na!"。Nakatingin sa orasan, tiningnan ko ito bago mag -6 ng umaga。Natulog ako bandang 1:30、Ang pagtulog ay tila isang tiyak na "banal na time zone."。"Ang Diyos (kung mayroon) ay nagpakita ng Kanyang ideya.。Kung hindi mo ito ginagamit、文字通り罰が当たる」と思いながら寝具を跳ね除けたのだった。