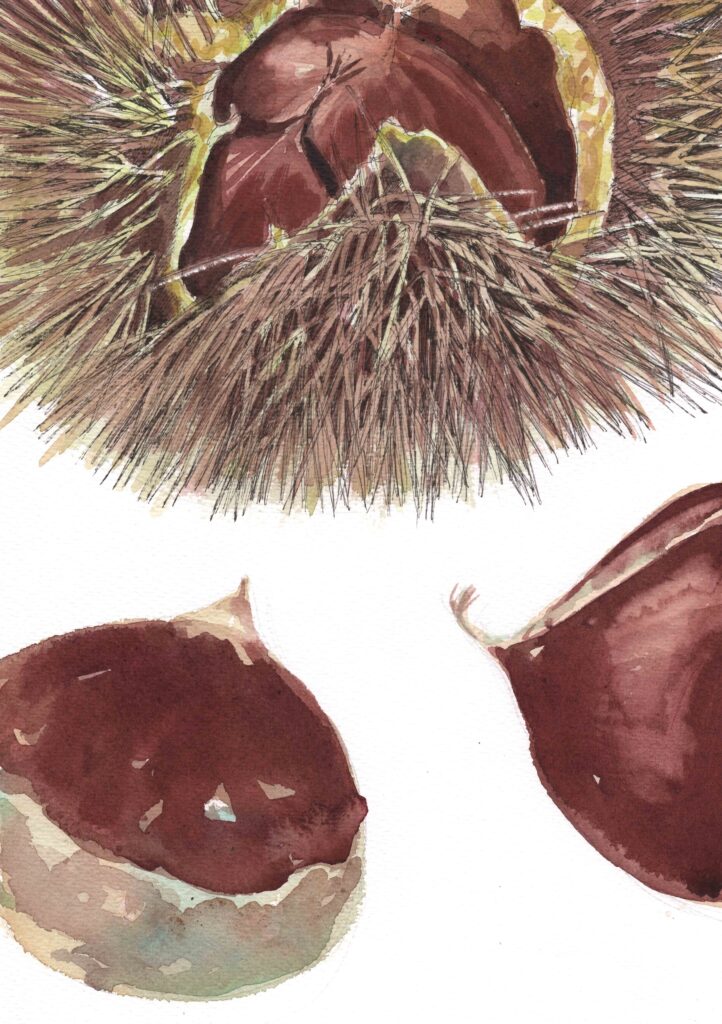Dünya sürətlə hərəkət edir。Bəzi şeylər daha da irəliləyiş əldə etdi、lakin、Bəzi şeylər degenerasiya və ya tərs。Dünya bu kimi hər cür istiqamətdə hərəkət edir。Belə ki、Eyni yerdə qaldığınızı düşünürsən、Nisbətən hərəkətdə olacaqsınız。
Ancaq、Mövcud yerin budur。Vaxt və məkan、Bir mənada bəşəriyyətin ixtirasıdır.。Bu yer üzündə fiziki cəhətdən yıxılır və kainatın tozuna çevrilir、Bir yerdə yeni bir həyat doğulursa、Oradan, "yeni" vaxt və məkan yenidən yaradılacağı ehtimalı var.。Astronomiyalara görə、Bugünkü insanlıq kimi təkamül ehtimalı、Görünür demək olar ki, sıfırdır。
Başqa sözlə、bizim、Xeyr、Yerdəki bütün həyatın indi "möcüzə" içində olduğunu söyləmək heç bir şişirtmə deyil。lakin、O möcüzə içərisinə baxır、Ziddiyyətlər çoxdur。Mükəmməl bir şeyin olmadığı aydındır。Və hələ、Bundan əlavə, yalnız "insanlıq" bunun bir hissəsidir、Bir düzgün cavab axtarır、Öz qanuniliyini təsdiq edərək bir-birlərini öldürürlər.。Bunun özündə bir ziddiyyət olduğunu başa düşməyə çalışmıram。
Yalnız insanlıq "sahibi" vaxt edə bilər。"Mənim vaxtım"。Bu nə möcüzədir?、Ölməzdən əvvəl bu barədə bir daha düşünmək pis bir fikir deyil、Mən düşünürəm。Bir az ağrılı olsa belə。"Hələ rəfdə həyat"。Mən heç bir şey çəkməmişəm、Vaxtım orada qalır。