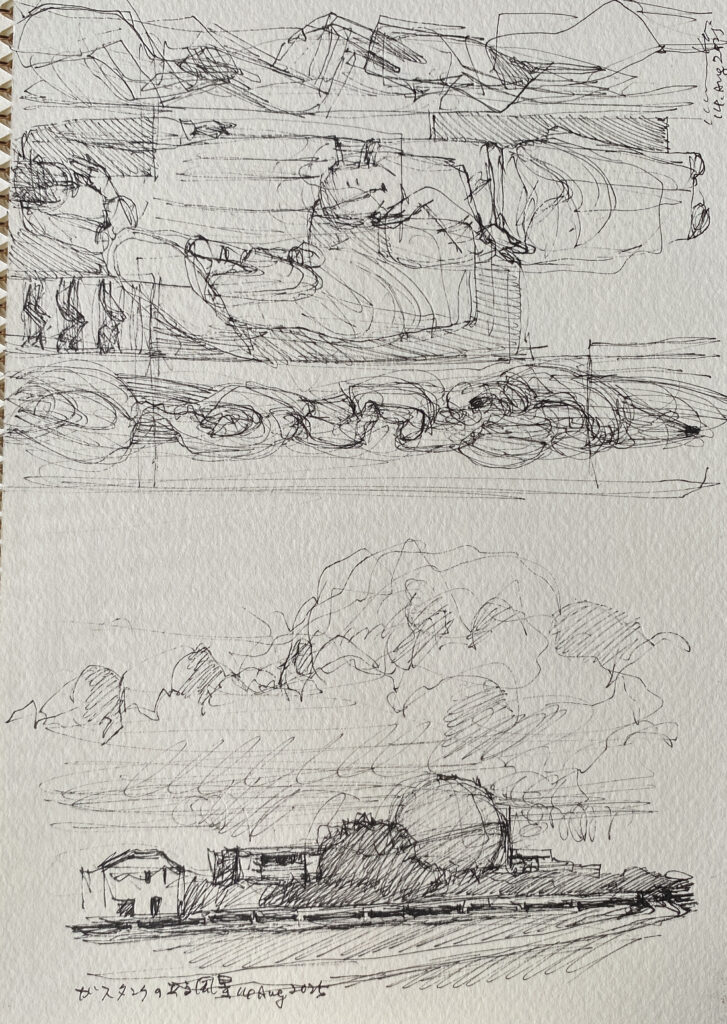ごく当たり前の話だが、「戦争をした方がいい」と口に出して言う人は少ない。誰もが「一応は」平和を望んでいる、かに見える。少なくとも表面上は。たまたま終戦の日前後に、トランプ・プーチン会談があったから、余計なことを考えていた。
戦争が終らない、無くならないのは「戦争をしたい(させたい)人がいる」からだ。現代社会では、歴史だの民族だのと理屈をならべながら、戦争開始のための結論としては「(我々の)平和を害する敵がいるから、自衛のためにそれを排除しなければならない」というワンパターンに行きつく。ウクライナ戦争しかり、イスラエルのガザ侵攻、イランへの爆撃しかり。すべては「自衛のため」。それには誰も逆らえない「魔法の言葉」。自分たちの“自衛”を口にしさえすれば、相手を皆殺しにしても構わないかのようである。そして大きな武力を持つ方が戦争をしかける。武力の小さいものはゲリラ戦を戦うしかない。
予想通りトランプ・プーチン会談は “ウィンウィン” というより “ラブラブ” だったらしい。プーチンは言いたい放題で、トランプは “恋人” への「白馬の騎士」になれて大満足の様子に見えた。「ウクライナをプーチンにプレゼントすれば、すぐ平和になる」とばかり、「ウクライナが存在するから戦争が起きる」というプーチンの狂った言い分を100%鵜呑みにした。当然プーチンは頗るご満悦のご様子。アラスカはロシアの植民地だと言わんばかりの、まるで自国のクレムリン宮殿で記者会見しているかのような、リラックスした雰囲気であった。
トランプはプーチンの前ではエカテリーナ女王を前にした門番のようにかしずくばかり。さすがに米国内でも、世界相手に関税戦争を吹っかける、傲慢なこの男の、この真逆な態度はどこから来るのか、と疑問の声もあがってきているようである。
「文明は(不可逆的に)進歩するが、文化はそうではない」とは誰の言だったか。nüüd、ロシアは文明的にも進歩というより退化し始めている(ように見える)。西側先進国(自らを「先進国」と呼ぶ、思い上った(そして恥ずかしい)言葉が笑わせるが)もまた、「アメリカ病」という長く沈殿していた悪い埃を吸っていたうえに、さらに「トランプ・プーチン病」という流行病に自己免疫反応するなど、胸(もしかすると「脳」?)を悪くして死にそうだという。―ある意味で、民主主義の自業自得―知恵なくばいっそ死をたまえ。